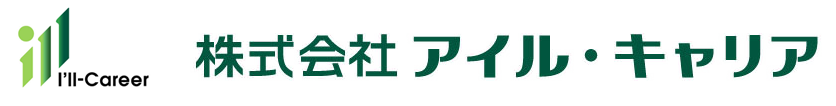ビジョン達成に必要な考え方やビジョン策定に必要な手順、
企業事例を解説
ビジョン達成に向けた考え方と策定手順は、企業の成長にとって不可欠なものです。この記事では、ビジョンを策定し、それを実現するための具体的な方法と、有名企業のビジョン設定事例を挙げて解説します。戦略的なビジョン策定が、企業の未来をどのように変えるか、そのポイントを押さえましょう。
ビジョンとは組織が実現したい将来構想を明文化したもの

ビジョンとは自社、自部門あるいは自チームとして中長期的に目指すべき将来の方向性や実現したい未来の姿を明文化したものです。言い換えると、企業や組織が果たすべき役割や存在意義を表す「ミッション」を実現した状態のことを指します。
ビジョンと共によく使われる言葉との違い
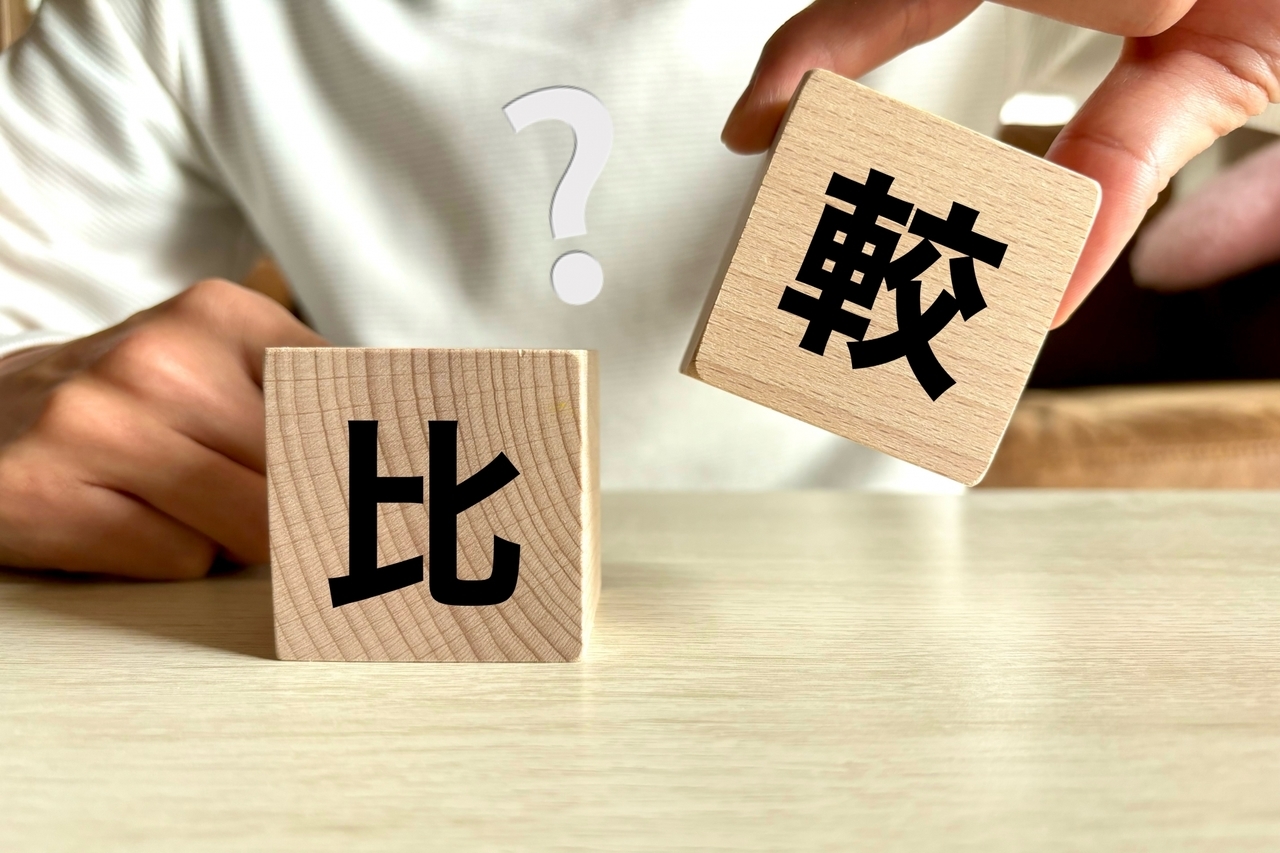
目標設定の具体例やフレームワーク、職種別の例文を解説ビジョンと共によく使われる言葉は下記の4つです。
- ミッション
- バリュー
- 経営理念
- パーパス
下記の表を使って、それぞれの言葉の意味を確認しましょう。
| 言葉 | 定義・意味 |
| ミッション | 日本語で「企業理念」や「社是」という意味を持ち、企業や組織が果たすべき役割や存在意義のことを指す。 |
| バリュー | 日本語で「価値」や「価値基準」を意味する。ミッションやビジョンと比較するとより具体的な価値基準になるため、メンバーの行動基準になることが多い。企業や組織が大切にする価値観を、社員が理解して具体的にイメージできることで、その実現に向けて行動を起こしやすくなる。 |
| 経営理念 | 経営理念は経営者の哲学や信念に基づいて、企業の根本となる活動方針を明文化したもの。 例)Googleの経営理念 「ユーザーにフォーカスすれば別の人もついてくる」 「スーツを着ていなくても仕事はできる」 「スピードが速いことは遅いことよりも良い」 「1つのことを最大限に行うことがベストな道である」 |
| パーパス | パーパスは「目的」を意味する言葉で、ミッションに近い言葉であるが、ミッションよりもさらに「社会的な貢献」を意識している点が異なる。 |
それぞれの言葉の意味を理解し、正しく使い分けられるようにしましょう。
関連記事
■ビジネスにおいて目標設定が必要な理由とは? 目標設定の具体例やフレームワーク、職種別の例文を解説
■株式会社アイル・キャリアが提供する意識改革・ビジョン形成講座
ビジョンが必要とされる理由
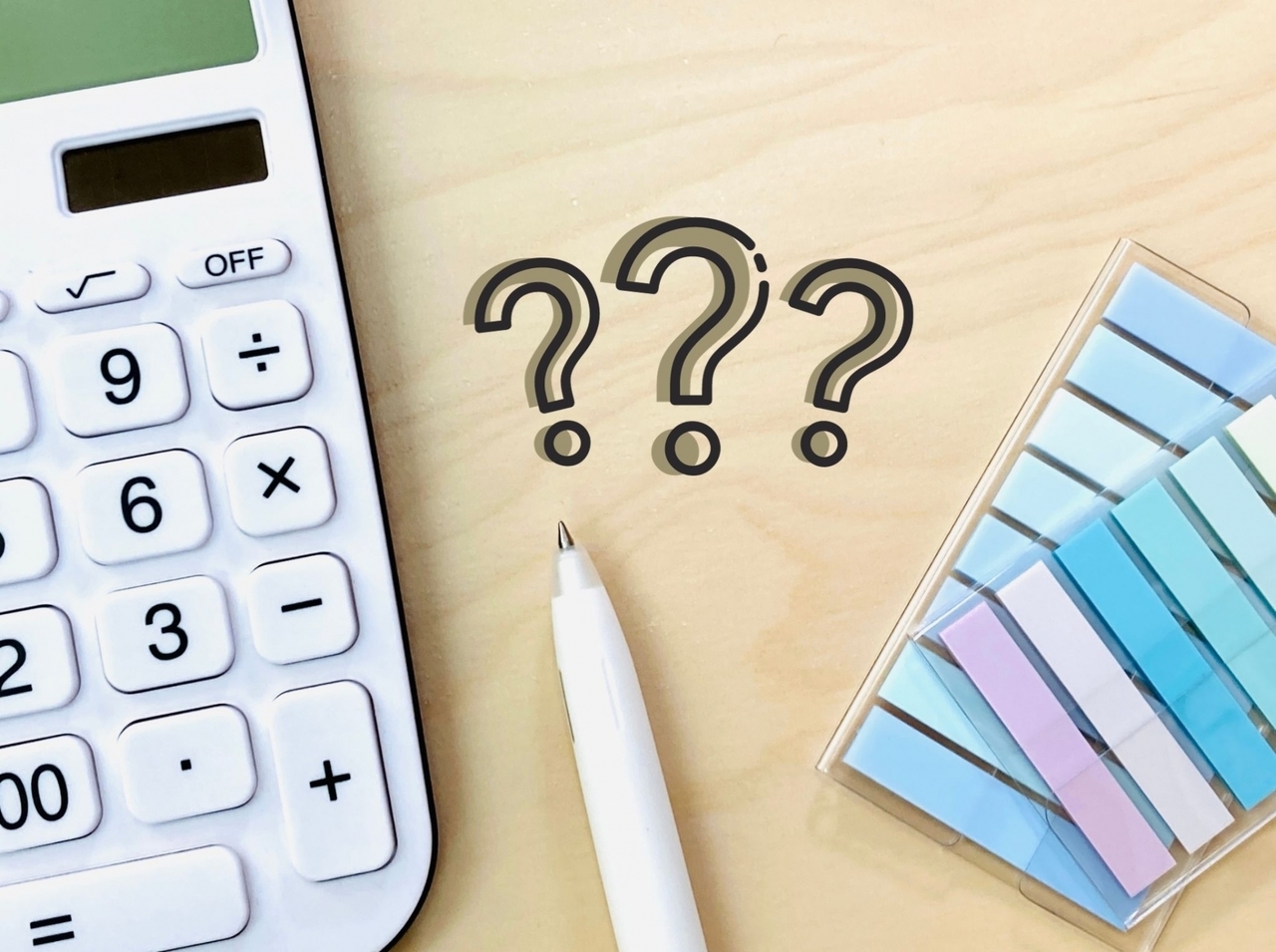
ビジョンが必要とされている理由は主に2つあり、下記の通りです。
1.社員が正しい方向に進めるようにするため
組織や社内にはさまざまな価値観を持ったメンバーが所属し、それぞれが別々のキャリアプランを描きながら働いています。目指す姿が提示されないと、目の前の短期的な目標達成だけを意識した働き方になってしまうでしょう。
人は「こうならなければいけない」「こうしなくてはいけない」といった義務感だけで継続的に成果を上げることはできません。チームとして目指すべき姿、「ビジョン」を提示してメンバーが向かう方向性を定めることで、メンバーのモチベーションを向上させ、成長を促進することにつながるのです。
2.ビジョンに合った業務行動かどうかを判断するため
数値目標だけを設定すると、「目標となる数値を達成しておけば良い」「数値につながるかどうかだけ考えれば良い」という考えに陥りがちです。このような考えが社内や組織内に浸透すると、クライアントとの関係性が弱まったり、主力商品やサービスの利益率が低下したりといったリスクが生じることがあります。
「なぜこのような目標数値が設定されているのか」「どうやって達成するべきか」といった行動指針を判断する基準としてビジョンを設定することで、これらのリスクを回避することにつながるでしょう。
ビジョン達成のために必要な7つのポイント

次に、ビジョンを達成するために必要なポイントについて解説します。
1. 内容はシンプルかつ、分かりやすくする
ビジョンを策定する際には、内容はシンプル、かつ分かりやすくすることがポイントです。ビジョンは社員が理解できないと意味がありません。難解な横文字や専門用語などは使わず、誰でも理解できるような内容にしてください。また、読む人によって解釈が異なるような言葉や用語も使用しないようにしましょう。
2. 達成可能な内容にする
シンプルかつ分かりやすい内容にするのに加えて、実現可能なものであることが大切です。あまりにも現実離れしていたり、実現が難しいと感じられるような内容だったりすると、社員を含めたステークホルダーの賛同を得ることは難しくなるでしょう。
3. トップダウンで社員に押し付けない
ビジョンを作成する際には、トップダウンで社員に押し付けてはなりません。トップダウンで社員に押し付けてしまうと、「社長が勝手に作った」と捉えられて賛同を得ることができず、名ばかりのビジョンになってしまう可能性があるからです。
できるだけ多くの社員にコミットしてもらうことを心がけましょう。社員の協力を得るためには、経営者から社員に参加を促すような働きかけをすることが大切です。
4. 意思決定を迅速に行う
社員を巻き込んでビジョンを定めたら、意思決定をスピーディーに行っていきましょう。達成すべき目標が見えているため、意思決定は比較的容易なはずです。意思決定のスピードを上げるためには、ビジョン達成のために「何をするべきか」「何をすべきでないか」を明確にして物事の優先順位を立てることが大切です。ビジョンの達成をできるだけスケジュール通りに進めましょう。
5. ビジョンに沿った未来予測の行動をとる
次に、ビジョンに沿って未来予測の行動をとります。ビジョンが決まっていれば、そのためにやるべきことが細分化できるはずです。業務フローを全体的に見直すケースも出てくるかもしれませんが、ビジョンに沿った先回りした行動がないとビジョンの達成は難しいため、ぜひトライしていきましょう。
6. 再度ビジョンを見直す
ビジョンが達成されない場合は、下記の原因が考えられます。
- ビジョンが分かりにくい
- ビジョンに具体性がない
- ビジョン達成をするための社員のモチベーションが低い
ビジョンが達成されない場合は、原因を把握し、再度ビジョンを見直すことが大切です。上記にもありますが、ビジョンを達成するためには、社員に「自分ごと」であると捉えてもらう必要があります。くれぐれも社員抜きでビジョンを考えたり、トップダウンで押しつけたりすることがないように気をつけましょう。
7. 社員へビジョンを浸透させる
ビジョンが決定したら、社員にビジョンを浸透させるための活動を行っていきましょう。繰り返しになりますが、ビジョンを達成するためには、社員の理解と納得が必要不可欠だからです。「なぜこのビジョンなのか」「どのような経緯でこのようなビジョンになったのか」といった細かい点も含めて、繰り返し、繰り返し、何度も社員に説明するようにしてください。
ビジョン策定の4つの手順

ビジョン策定にあたっては、下記4つのステップを踏んでいきましょう。
現在の自社事業を正しく把握する
まずは、自分自身に下記のような質問を問いかけ、現在の自社事業を正しく把握しましょう。
「あなたの会社は、誰にどのような商品・サービスを提供し、どのような価値をもたらしているのか?」
「あなたがターゲットとする顧客層はどのような人々で、何に対していくらの対価を支払ってくれているのか?」
これらを考えることで、今後進むべき方向性や未来の姿をより具体的にイメージできるようになるでしょう。
自社を取り巻く環境を把握する
次に、自社を取り巻く市場や直接的な競合の現状、今後の成長性などについて把握します。この際、客観性を保つことが重要となるため、財務諸表やIR資料などの公開資料や市場調査会社のレポートなどを活用することがおすすめです。
そして、売上高や自社の強みや弱みをベースにポジショニングマップを作っていきましょう。今後の成長性については、競合を含めた市場全体の現状を把握しながら、今後の事業環境などを踏まえて予想しましょう。
会社の価値観をしっかりとした議論で明確にする
経営陣だけでなく社員も含めて全社で、「仕事をする目的」について話し合う場も必要となります。仕事の目的には、下記のようにさまざまなものが挙げられるでしょう。
- お金を稼ぐため
- 生活するため
- 地域社会に貢献するため
- 人々の生活をより良いものにするため
話し合いを進める中で、会社の歴史や文化など会社のレガシーとなる情報を全社員に共有することがポイントです。その上で、社員1人ひとりが何を大切にしているのか、何を守っていきたいのかといった考えを率直に話し合います。議論を繰り返しているうちに、共通となる価値観が見えてくるでしょう。この共通の価値観こそが、ビジョン策定には、とても重要となります。
会社の将来の姿をイメージする
下記3つについて考えたことや話し合ったことをもとに、会社のあるべき姿をイメージしましょう。変化が激しい今の時代には難しいことだと思いますが、出来れば、5年後や10年後のイメージが共有できると良いでしょう。
- 現在の自社事業の内容
- 自社を取り巻く環境
- 社内における共通の価値観
例として、以下のように事業計画などと照らし合わせた具体的なイメージを描きましょう。
- 現在の自社事業を継続させながら規模を拡大させる
- ターゲット層を拡大して新規顧客を獲得する
- 自社製品やサービスのラインナップを拡充する
有名企業が掲げるビジョン事例

最後に、下記3社のビジョンの事例を紹介します。
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キャノンマーケティングジャパン株式会社では、「社会・お客さまの課題をICTと人の力で解決するプロフェッショナルな企業グループ」を2025年のビジョンとして定めています。
このビジョンを実現するための基本方針は4つあり、下記の通りです。
- 利益を伴ったITS事業拡大
- 既存事業の更なる収益性強化
- 専門領域の強化・新たな事業の創出
- 持続的成長に向けたグループ経営
キャノン株式会社の経営ビジョンについてさらに詳しく知りたい人はこちら
KDDI株式会社
KDDI株式会社は、経営ビジョンと中期経営戦略を分けて掲げている点が特徴的ですが、経営ビジョンをベースに中期経営戦略を策定しています。2022年に掲げた経営ビジョン「KDDI VISION 2030」は「『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会を作る」です。
KDDI株式会社の経営ビジョンについてさらに詳しく知りたい人はこちら
株式会社ファーストリテイリング
株式会社ファーストリテイリングでは、「服のチカラを、社会のチカラに。」を経営ビジョンのサステナビリティステートメントとして掲げています。また、「People(人)」、「Planet(地球環境)」、「Community(地域社会)」3つのテーマに、下記の6つの重点領域を特定しています。
- 商品と販売を通じた新たな価値創造
- サプライチェーンの人権・労働環境の尊重
- 環境への配慮
- コミュニティの共存・共栄
- 従業員の幸せ
- 正しい経営
株式会社ファーストリテイリングの経営ビジョンについてさらに詳しく知りたい人はこちら
まとめ
ビジョンを達成するためには、明確な目標設定と具体的な行動計画が必要です。ビジョンの策定にあたっては、社員が一丸となって議論し、共に会社の価値観を明確にしながら創り上げていくことが大切です。この記事で紹介した方法と事例を参考に、自社に合ったビジョンの策定とビジョン達成に必要な思考法と手順を理解し、自社の成長戦略に活かしましょう。
関連記事
■ビジネスにおいて目標設定が必要な理由とは? 目標設定の具体例やフレームワーク、職種別の例文を解説
■株式会社アイル・キャリアが提供する意識改革・ビジョン形成講座
この記事の監修者
株式会社アイルキャリアは、お客様ごとに抱える課題や目標に合わせたオーダーメイドプログラムで”学び”を提供する研修会社です。官公庁・自治体から上場企業、医療法人や学校法人まで様々なお客様に対して、ご要望と時流をふまえた必要な”学び”を、新人から管理職まで幅広く提供し、組織の人材育成を支援しております。特徴としては、その研修で達成したい目標(行動変容)の先にある成果、パフォーマンス(行動変容の結果得らえるもの)までを意識してプログラムを作成することにあります。
サイドメニュー
- ★選ばれる理由●
- 講師紹介
- 事例一覧2
- 川口鋳物工業協同組合様
- 愛媛県研修所
- 佐賀県自治研修所
- 蕨市役所
- IAC様
- 静岡県湖西市役所
- 佐倉市役所
- 千葉市
- 大分県自治人材育成センター
- 事例一覧3
- 下田市役所
- 宮崎県市町村職員研修センター
- 鹿児島県
- 江戸川区
- 足利市
- 宮崎県市町村
- 伊勢崎市
- 労働生産性の向上-1
- タイムマネジメントが上手い人の特徴とスキル:仕事の生産性を高める秘訣とは?
- 【タイムマネジメント研修とは】 実施する理由や効果まで包括的に解説いたします
- タイムマネジメント方法の完全ガイド
- タイムマネジメント能力を高めるための実践ガイド
- 効果的なタイムマネジメント研修の選び方
- 「仕事の見える化」は業務の効率化に必須 【タスクを可視化する研修を紹介】
- 仕事の優先順位づけとは? 業務を効率化するためポイント・研修を紹介
- イレギュラー対応力を分析して生産性を上げる 【すぐ使えるスキルから研修まで】
- チームパフォーマンス向上研修で変わる職場 【組織としての成長を目指して】
- 労働生産性の向上-2
- 正しい育成方法で新人・若手社員の早期育成を実現する 【研修で意識すること】
- 仕事の効率化に結びつく具体的な方法を提案 【即効性のある研修も紹介】
- 自律型人材とは?求められる背景やメリット・デメリット、育成方法を解説
- オンボーディングは早期離職を解決するカギ!実施時のポイントや事例も紹介
- 【新人の早期育成】 即戦力を育てるために取り組むべきことを解説します
- 時間管理の効果的な方法とツールの徹底解説
- 生産性を向上させるための秘訣とは 【組織レベルから個人まで対応】
- 時間の使い方が上手になる方法は? 成果が上がる時間管理術を紹介
- プレイングマネジャーの仕事術とは?役割や効率化のコツを解説
- 労働生産性の向上-3
- プレイングマネジャーの悩みを解決する時間管理術とは?
- タレントマネジメントとは?導入手順やメリット・デメリットも紹介
- テレワーク・在宅勤務導入後の労働時間管理におすすめの方法 3選
- スピード仕事術を身に付けよう!仕事を効率化させるテクニック
- タスク管理を上達させて仕事を効率化させよう! 役立つツールの紹介も
- 企業におけるエンゲージメントの意味とは? 向上させる方法もあわせて解説
- ハラスメントとは? 会社で重視すべき7つのハラスメントと防止策を解説
- リスキリングとリカレントの違いとは? 導入するメリット・デメリットを解説
- 社内コミュニケーションを活性化させる9つの施策を解説!他社の成功事例も紹介
- 労働生産性の向上-4
- Z世代の特徴や欠点に合わせた効果的な育成方法とは?NGな叱り方も紹介
- VUCAとは?今の時代に適した人材を育成する方法をわかりやすく解説
- 厚生労働省も推進するキャリア自律とは?定義やデメリット・メリットを紹介
- 人事担当者必見!戦略人事の成功事例8選&成果を出す実行ステップ
- 人的資本経営とは?企業・自治体が押さえるべき背景と人材育成の成功ポイント
- 残業削減のための研修や方法を解説!働き方改革で求められる施策
- Z世代も納得!「タイパを極める」ビジネススキル習得術
- ワークスタイル分析で生産性を高める 【すぐに使えるスキルから研修まで】
- 複製用
- 働き方-1
- キャリアデザインとは? 意味や必要性、具体的な支援方法を徹底解説!
- キャリアデザインシートの作成方法と活用の秘訣
- キャリアデザイン研修の効果と実践例
- キャリアデザインの重要性とその実践方法
- 【キャリアの定義とは?】 従業員のキャリア開発が必要な理由を解説
- キャリアの棚卸しの方法とステップガイド
- キャリアチェンジを成功させるための具体的な方法
- どんなキャリアを積みたいかわからない人への、 キャリアプラン作りの基礎解説
- キャリア戦略の重要性 | 人生設計や転職時に役立つワークシートを紹介
- 働き方-2
- キャリアデザインシートの書き方例 | 構成の方法やコツを解説
- キャリアゴールとは何か? ゴール設定の必要性や具体的な設定手法、事例を紹介
- ビジョン達成に必要な考え方やビジョン策定に必要な手順、 企業事例を解説
- キャリアプランニングとは何か? メリットや重要性、実施方法まで詳しく解説
- ビジネスにおいて目標設定が必要な理由とは? 目標設定の具体例やフレームワーク、職種別の例文を解説
- キャリアアセスメントとは? メリット・デメリットや活用できるツールを紹介
- 「生きがいを支える5つの大切なこと」
- 人生の満足度を高める方法
- 今注目の「働き方改革」とは?具体的な取り組みと課題
- 働き方-3
- ワークライフバランスの見直しや実施が 企業と社員にとって必要な理由
- 仕事と家庭の両立法 | 無理なくこなすためのコツ
- 研修理論-1
- 「研修は、人の能力を拡張する」が鍵に… ~「あなたに頼んでよかった」を生み出す、人の領域~
- 2026年 人材育成のトレンド
- 人材育成は、「人が決める場」をつくる仕事だ!
- 「High Impact Learningモデル」
- 「ラーニングピラミッド」
- テクノロジーと人間力を融合した学びの未来
- 「カークパトリックモデルの4段階評価」
- 「パーソナライズされた学習は、誤った仮説に基いている」
- 「知識の保持や適用には望ましい困難が必要」
- 研修理論-2
- 「学習の5段階」
- 「研修のゴールは行動変容ではない!?」
- オンライン研修とは?メリット・デメリット、始め方について徹底解説
- 「サクセス・ケース・メソッド」
- 「プランド・ハプンスタンス・セオリ(ハプンスタンス・ラーニング・セオリ―)」
- 「エキスパート(専門家)になるには」
- ニュース一覧
- 調達企業一覧(補足資料)
- 監修者
- 資料請求ありがとうございました
- 求人情報
- ピックアップ!
- 人材育成に関するコラム
- お客様の声(2022年度)
- お客様の声(2021年度)
- お客様の声(2020年度)
- 書籍購入
- 特典動画のお申し込み確認
- ダイレクトメール
- メディア掲載・その他
- 個人情報保護方針
- 無料個別相談会(オンライン)
- 無料個別相談会のお申し込み確認
- メールマガジン登録
- メルマガ登録ありがとうございました
- メルマガ登録を解除いたしました
- 研修一覧