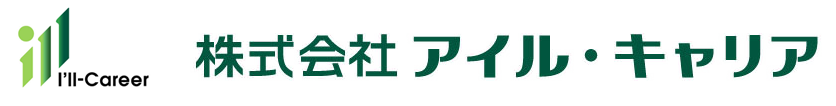バックナンバー 2023年
- 396号 学習の科学 Dunning-Kruger効果とは?
- 395号 オンライン研修の教材は、紙か画面か?
- 394号 もっとも難しい精神面育成の鍵は…
- 393号 研修の学びには、望ましい困難が必要…
- 392号 続編!ものごとを先延ばしにする原因は?
- 391号 大谷選手に見る強みの活かし方…
- 390号 e-ラーニング有効活用のコツ…
- 389号 キャリア自律に役立つことは?
- 388号 研修効果を上げる研修設計3つのポイント
- 387号 新人研修の登壇前に読んでいただきたい話…
- 386号 MVPの大谷選手がスゴイ理由は…
- 385号 非効率なことは悪なのか!?
- 384号 メタバースは研修で使えるの?
- 383号 新入社員の離職を防ぐために…
- 382号 衝撃!ChatGPTがメルマガを…
- 381号 戦略人事が果たすべき役割
- 380号 人を見る目を養うには…
- 379号 人的資本経営とは?
- 378号 リスキリングを分かりやすく解説
- 377号 ナポレオン流、目標設定術とは?
- 376号 年始に20の教訓…
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
先日、
三菱UFJ銀行が、
窓口業務の7割をデジタル化する
というニュースを目にしました。
高齢者などの顧客層が厚いメガバンクが
デジタル技術導入に舵をきる動向は、
個人的に興味深いものがあります。
とはいえ、
デジタルリテラシーが不足する
高齢者などにもやさしいサービスに
落ち着いてくれることを切に願います…。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「オンライン研修の教材は、紙か画面か?」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この春採用された新人も
職場に配属されて3か月目…、
そろそろ、
メンタル、フィジカル、仕事のスキル…、
さまざまな面で差が出てきているのでは
ないでしょうか。
今年の新人のフォローアップ研修は、
万全でしょうか?
もし、これから何かを追加しようと
ご検討の場合は、
いまからでも、まだ間に合います。
「メンター研修」
“Z世代”と言われる新人たちへの
具体的な関わり方を、
仕事にプライベートに、
数多くのZ世代に接している
弊社の講師陣が、具体的にレクチャーいたします。
これからメンターになる方に向けて、
Z世代の特性も踏まえながら、
メンターとしての心構えから、
コミュニケーションスキルまで、
学んでいただきます。
集合研修、オンライン研修はもちろんのこと、
e-ラーニング(動画)の提供も可能です。
個別相談会は、こちらから。
e-ラーニング(動画)は、こちらから。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「学習の科学 Dunning-Kruger効果とは?」
というテーマでお届けします。
仕事において、
いま現在の自分の能力を正しく把握し、
それに応じた努力をすることは重要です。
しかし、
実際のところ、
私たちにとって自分の能力を正確に理解したり、
把握することは難しいようです。
コーネル大学の心理学教授、
David Dunningと、
ニューヨーク大学の心理学教授、
Justin Krugerの研究によれば、
スキルが低い人の方が、
スキルの高い人よりも
自分の能力を高く見積もる傾向にある一方、
スキルの高い人は、
実際よりも自分の能力を
低く見積もる傾向にあるそうです。
つまり、
能力が低い人の方が、
自分の能力を過信しがちだということです。
この研究は、
他の多くの状況でも再現されており、
※Dunning-Kruger 効果と呼ばれるようになっています。
※Dunning-Kruger 効果は、
『Journal of personality and social psychology』に掲載
KrugerとDunningによれば、
スキルの低い人は自分のやっていることや
理解度を客観的にモニタリングし、
評価するスキル(メタ認知スキル)が不足しているので、
自分がそのスキルを適切に行うことが
出来ているかどうかを判断できないのです。
たとえば、
良いメールを書こうとしたら、
そのメールがよく書けているかどうかを
自ら判断できる能力が必要です。
しかし、
スキルの低い人は、
そもそも良いメールとは、
どのようなものかが分かっていないので、
適切なメール、良いメールとは
どうあるべきかにもとづいて
書くことが出来ないのです。
このDunning-Kruger 効果
の理由については、
多くの学術的な議論がされていて、
研究者の中には、
西欧以外の社会では、
「謙虚」になることの大切さを
教えられる場合があるので、
これは、
西欧人特有の現象だという人もいるようです。
いずれにしても、
何かに関して初心者であるうちは、
自分が何を学ぶ必要があるのか?
それをどう行えば適切であるのか?
自分が正しく出来ているかどうかの
判断が出来ないことは確かです。
だからこそ、
何かを新たに学ぶ時は
適切な指導者のもとで行った方が
良いということになります。
対面研修でも、
オンライン研修でも、
e-ラーニングでも、
アイル・キャリアは、
グローバルトレンドや
理論に裏づけされた研修プログラム、
ラーニングデザインが可能です。
私どもで、
お役に立てることがあれば、
お気軽にご連絡下さい。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
先月26日、
「Chat(チャット)GPT」
のiPhone用アプリが
リリースされましたね。
初公開からここまでに要した期間は、
約6カ月。
凄いスピード感ですね…。
早速、
ダウンロードし、
私も使ってみました。
あくまでも
個人的な感想ですが…、
音声認識レベルが
少し上がったような気がします。
これで機動力も
アップ出来そうな予感…。
とはいいつつも、
使い方と回答の鵜呑みには、
要注意ですね!
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「もっとも難しい精神面育成の鍵は…」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日、6月1日より、
弊社の事務スタッフは、
カスタマーサクセスに生まれ変わりました。
それに伴い、
新たな仲間の募集も開始致します。
詳細は、後日、ご案内致しますが、
お知り合いに、
ご興味ありそうな方がいらしたら、
弊社HPのお問合せフォームから
お気軽にご連絡下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「オンライン研修の教材は、紙か画面か?」
というテーマでお届けします。
人間が学習するには、
紙で読んだ方が良いのか?
パソコン、タブレット、スマホなどの
画面で読んだ方が良いのか?
コロナ禍でオンライン研修が増え、
受講スタイルも多様化する中、
色々と調べていました…。
結果、
以下のような記事にたどり着きました。
忙しい方も多いと思うので、
先に、ポイントをお伝えすると…、
「パソコンやスマートフォンの
ディスプレイで何かを読むことが、
理解の妨げとなる場合がある」
ということです。
以下、
学習およびパフォーマンスコンサルタントの
Patti Shank氏の記事要約です。
出典先:
https://www.td.org/insights/what-do-you-know-do-we-learn-less-from-screens
デジタル画面は、
紙に比べて理解を低下させます。
デジタル画面上のテキストを読む場合と、
印刷物を読む場合の違いについての研究は、
過去20年以上にわたってさまざま行われており、
その結果もさまざまです。
ここでは、
いまのところ真実と考えられている
研究結果をご紹介します。
●記憶
画面で読むより印刷物で読んだ方が、
内容をよく思い出せることを示す研究があります。
印刷物は、デジタル画面にはできないような方法で
記憶を助けている可能性があります。
印刷物は、コンテンツの場所を特定しやすく、
構成が明確なので、内容を適切な構成で記憶できることが、
記憶を助けていると考えられます。
●理解
画面で読むと、印刷物で読んだ場合より
理解が低下することを示す研究があります。
画面のナビゲーション方法に問題があることが、
理解を妨げていることがその理由として考えられます。
紙の場合は、特定の部分を見つけて読み直したり、
特定の部分にメモを書くことが簡単ですが、
画面の場合は、必ずしもそれを簡単に行うことができません。
●読むスピード
紙の場合より画面で読んだ場合のほうが、
読むスピードが遅くなることは、
多くの研究で明らかになっています。
テキストが長くなると読むスピードが低下することが、
その理由のひとつとして考えられます。
※レスポンシブデザインの場合、
デザイナーが文章の長さをコントロールできません。
※レスポンシブデザインとは
Webサイトのデザインを
「閲覧ユーザーが使用するデバイスの画面サイズに応じて
表示を最適化するデザイン」をいいます。
●画面/紙のどちらが好まれるか
ほとんどの人は、画面よりも紙で読むことを好みます。
これは、画面の解像度や読みやすさなどが理由として考えられます。
人はそもそも、紙で読む方に慣れているという理由もあります。
ということで、
ここまでの内容で、
今日のまとめに入っても良いのですが、
せっかく、
ここまで長文を読んで下さったので、
おまけの話を1つ。
冒頭ご紹介した、
「Chat(チャット)GPT」
のiPhone用アプリで
音声認識を使ってASKしてみました。
回答は、以下の通りです。
学習方法については、一概には言い切ることができません。
学習におけるメディアの選択は、
個人の好みや状況によって異なる場合があります。
ただし、
いくつかの科学的研究結果と一般的な考え方に基づいて、
いくつかの要素を考慮することができます。
●理解と記憶:
いくつかの研究では、紙の本を読むことが
情報の理解や記憶において有利であると示されています。
紙の本では、文章の構造や物理的なページの配置によって
情報を整理しやすくなる場合があります。
また、ページをめくることによって物理的なアクションが伴い、
それが記憶の促進につながると考えられています。
●集中力と没入感:
デジタルデバイスは、インターネットや
他のアプリケーションに容易にアクセスできるため、
学習中の集中力や没入感を妨げる可能性があります。
一方、
紙の本はそれらの誘惑から解放され、
学習に集中することができるとされています。
●読書体験の個人差:
学習メディアの選択は、個人の好みや
学習スタイルによって異なる場合があります。
一部の人々はデジタルデバイスでの学習を好む一方、
他の人々は紙の本を好む場合もあります。
自分自身が最も効果的な学習方法を見つけるために、
両方のメディアを試してみることが重要です。
最終的には、
学習におけるメディアの選択は
個人の状況や好みに依存します。
どちらの方法でも学習が可能ですが、
自分自身の学習効果を観察し、
最も効果的な方法を見つけることが重要です。
また、デジタルデバイスを使用する場合は、
学習に集中できる環境を整えることも重要です。
とまあ、
もっともらしい回答が返ってきました。(笑)
ChatGPTを始めとした
生成AIを仕事で使うかどうかは
賛否両論ありますが、
今日の私が、
お伝えしたかったことは…、
人材育成、研修に携わる身としては、
オンライン研修などを実施する時、
受講者が学習する環境として、
どのようなものを提供するのか?
たとえば、教材は、
紙が良いのか?
デジタルの画面が良いのか?
ということについて、
少し知識をもっておくことも
大切ではないかということでした。
対面研修でも、
オンライン研修でも、
e-ラーニングでも、
アイル・キャリアは、
グローバルトレンドや
理論に裏づけされた研修プログラム、
ラーニングデザインが可能です。
私どもで、
お役に立てることがあれば、
お気軽にご連絡下さい。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
お知らせです。
次月より、
メール配信システムを
変更したします。
それによって、
一部、配信されない方が
出てくる可能性がございます。
万が一、
次週より配信されず、
引き続き、購読をご希望される場合は、
お手数お掛けしますが、
お問合せフォームより、
ご連絡いただけますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「研修の学びには、望ましい困難が必要…」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ここ最近、
仕事にプライベートに、
目の前に起こる出来事から、
自分が何を大切にしているのかが、
改めて、ハッキリ理解出来ました。
大切にしている価値観は何か?
価値基準は何か?
何のために、このメルマガを書き続け、
何のために、いまの仕事を続け、
何のために、日々の仕事の効率を考え、
何のために、運動し、
何のために、毎日、母に電話し、
何のために、家族との時間を過ごしているのか…
意外と自分のことは、
分かっているようで、
分かっていないもの。
でも、
自己理解が進むことは、
働くことや人生全体に大きな意味をもつ
そう感じています。
とはいえ、
日々、やることが多い状態で、
自己理解を深めることは、
とても困難です。
そこで、
仕事の時間中に、
内省する時間として、
キャリアデザイン研修という
選択肢があると考えております。
実は、
全然、私も知らないうちに、
以下2つの研修比較サイトで、
弊社が取り上げられています…(笑)
https://www.biz.ne.jp/matome/2006056/#chapter-10 (比較BIZ)
https://imitsu.jp/list/training/career-design-training/#Ujo7Ci3rj_ (アイミ
ツ)
キャリアデザイン研修をご検討の場合は、
弊社HPのお問合せフォームから
お気軽にご連絡下さい。
個別相談会も実施しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「もっとも難しい精神面育成の鍵は…」
というテーマでお届けします。
「人的資本経営の時代」
企業を中心に様々な取組が行われています。
「経営の神様」といわれ、
一代でパナソニックフォールディングスを築き上げた
かの松下幸之助氏は、
創業初期の頃、
「松下電器は何をつくるところか」
とお得意先から聞かれたら、
「松下電器は、人をつくるところです。
あわせて電気製品もつくっております。」
そう答えるよう、
従業員に伝えていたことは有名な話です。
「人的資本経営」とは、
「事業は人なり」
まさに、
そういうことなのかも知れません。
組織は、
事業の目的を達成するために、
どういう人材を採用し、
どういう教育、育成をするのか?
そして、
そこで鍵となるのが、
いかに、エンゲージメント、
モチベーション高く、
イキイキと働いてもらうか?
という課題があるのでしょう。
人材育成の面から考えると、
社員、職員のエンゲージメント、
モチベーションアップは非常に重要です。
しかし、
実際には、
この精神面の育成が
最も難しいとも言われています。
この部分の育成が上手くいかず、
仕事の効率が低下したり、
離職率の向上に繋がってしまっている
組織もたくさんあるのが現状です。
そこで、
今回は、
「期待理論」をご紹介しながら、
いまこの時代、
この瞬間のモチベーションについて
考えてみたいと思います。
まず、
「期待理論」とは、
1964年、イェール大学の経営学・心理学教授、
ヴィクター・H・ヴルーム氏が提唱したとされている
モチベーション理論の基礎と言われるものです。
一言でいえば、
人は、目標や成果に対して報酬、
努力が報われる結果が分かっていれば、
行動に対してモチベーションが上がる。
乱暴な言い方をすれば、
頑張ったら報われるんだと
分かっていたらやる気になる
というようなものです。
その後、
1968年に、
レイマン・ポーター氏とエドワード・ローラー三世が、
ヴルームの期待理論をベースとして改変、改良。
「ポーターとローラーの期待理論」
を提唱しました。
ヴルームの期待理論との相違点は、
報酬の大小と魅力の度合いによって
モチベーションが変化すると
考えられていることにあります。
努力した結果として得た報酬の満足度によって、
その後の行動(モチベーション)の度合いが決まる。
乱暴な言い方をすれば、
頑張って得た報酬に満足すればするほど、
やる気が上がる。
そんなイメージです。
現在は、
ダニエル・ピンク氏提唱の
「モチベーション3.0」
内発的動機付けが重要視されていますが、
私の個人的な意見としては、
内発的動機付けは、
いまこの時代にも、とても重要。
でも、
働く環境、制度の変化が激しい
この時代には、
外発的動機付けにも、
改めて、目を向ける必要性があるのではないかと
考えています。
たとえば…、
ジョブ型雇用が導入される中で、
他社や他の団体に、
採用負けしないよう、
優秀な人材、
高度なスキルをもった人材には、
高額な報酬を払って採用する
こういったことが
起きているからです。
採用時だけでなく、
働いて生み出した成果に対しても、
これまでとは違った形で評価することが
必要になってくるのではと感じています。
もちろん、
外発的な報酬は、
金銭的な報酬だけではありません。
いずれにしても、
これだけ変化が激しくなれば、
何か1つの理論だけに捉われるのでなく、
さまざまな理論や切り口から、
採用、育成、評価といったことを
考えていかなければならないはずです。
そして、
その際、
組織は人で出来ていることから、
社風や働く人の感情、気持ちを大切にした経営、
組織運営、人事制度、育成制度の構築が
重要になってくるのではないかと感じています。
私どもで、
お役に立てることがあれば、
お気軽にご連絡下さい。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
昨日に続いて、
今日の東京も30度超え。
真夏日になるようです…。
熱中症には、
十分気をつけつつ、
いまからでも、
“暑熱順化”で、
これからの暑さに
備えていきたいですね。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「続編!ものごとを先延ばしにする原因は?」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以前、このメルマガで、
BNPL(バイ・ナウ・ペイ・レイター)など、
手軽な後払い決済手段を使う若者が増えている
という話をお伝えしました。
また、
こういった手軽な
決済手段を使うことによって、
金銭感覚が緩んで、
支出を増やしてしまう人が
増えているともお伝えしました。
景気を良くするために、
お金を使うことは必要ですが、
行き過ぎた支出、
ムダな支出は、
将来に対するお金の不安を生み、
将来のお金に対する不安は、
キャリア形成に少なからず
影響を与えると考えられます。
したがって、
社員、職員の
研修プログラムの1つに、
マネープラン研修、
あるいは、
マネープランを絡めた
キャリアデザイン研修の導入を
おススメしております。
投資については、
私も、20年弱のキャリアがありますので、
それなりに語れますが、
弊社では、
資産運用の専門家、
IFA (独立系ファイナンシャルアドバイザー)
の講師によって提供することも可能です。
マネープランを絡めた
キャリアデザイン研修をとお考えの場合は、
弊社HPのお問合せフォームから
お気軽にご連絡下さい。
個別相談会も実施しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「研修の学びには、望ましい困難が必要…」
というテーマでお届けします。
以前、
このメルマガでもご紹介した、
学習の5段階、覚えていますか?
(学習の5段階)
1,無意識的無能
知らないし、出来ない
2,意識的無能
知っているけど出来ない
3,無意識的有能
考えると出来る
4,意識的有能
考えなくても出来る
5,無意識的有能に、意識的有能
どこからでも教えることができる
という内容でしたが、
研修の学びをデザインする時は、
受講者のレベルを確認、
または、予測し、
この5段階を意識して設計するだけで、
その効果は、だいぶ変わって参ります。
たとえば…、
「すでに受講者が知っている内容を
講義するのは意味がない」
そんな話をする方も
いるようですが、
理論上、
そうとも言えないんです。
というのも…、
知っている内容でも、
出来ているのかどうか?
出来ていたとしても、
どのレベルで出来ているのか?
あるいは、
どこからでも、
他人に教えることが出来るのか?
といったことを
本人が腹落ちすれば、
学びは一気に深まるからです。
もちろん、
簡単すぎる学習は、
あまり意味がありません。
良質な学びには、
適度な難しさが必要なのです。
そこで、今日は、
Robert Bjorkの
「望ましい困難(desirable difficulties)」
という話を紹介します。
稀に、
研修の投影資料とテキスト、
レジメの記載内容を同じにして欲しい。
そんなお声をいただくことがありますが、
それは、
受講者の立場からいうと、
よく分かる話です。
なぜなら…、
多くの場合、
受講者はテキストを読み返すなど
安易な学習方法を好むからです。
でも、
Robert Bjorkの研究によると、
受講者が好む方法と、
知識の保持や適用に適した方法は
異なります。
結論としては、
研修の効果、
学びを深めるためには、
受講者にとって、
「望ましい困難」
を意図的に設定することが
必要なのです。
「望ましい困難」
があることによって、
腹落ちする深い学びへと
導かれていくからです。
良質で深い学びには、
それ相応、受講者自身の努力が
必要ということです。
そして、
その努力は、
以下3つの要素を押さえて
行うことが必要です。
1,すでに知っていることに、
今回の学習内容を関連付ける。
2,学習内容の重要な部分を、
受講者が自分の言葉で表現する。
3,実務と同じ方法で、
学んだ知識やスキルを実践する。
以上、
望ましい困難とは、
短期的な記憶ではなく、
研修内容の長期的な記憶と
腹落ちするための努力を
必要とするような
学習項目の1つとなります。
研修プログラムの設計など、
学びをデザインする時は、
こういったことを意識しながら
行うことも必要です。
それでは、
今日のまとめです。
研修プログラムに、
受講者が知っている内容を入れることは、
無駄とはいえない。
受講者が好む学習方法と
研修効果は一致する訳ではない。
結論として、
「研修の学びには、望ましい困難が必要…」
というお話でした。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
今朝、
関東で震度がありました。
先日の能登に続いて、
しばらくは、注意が必要ですね。
お互い気をつけて参りましょう。
ちなみに、私は、
昨晩、熊本入りし、
本日から2日間、こちらで登壇です。
この時期は、
5月病の症状に悩まされる人
もいるため、
頭の片隅にいれつつ、
研修中の学びを
最大化して参ります。
ちなみに、
5月病の対応策は、
ストレスを溜めないこと。
具体的な方法論として、
1,親しい人たちとの交流
2,笑う
3,仕事から離れた趣味をもつ
※以上、厚労省サイト「こころの耳」より
といったことが効果的のようです。
もし、身近に、
心当たりがあればご参考までに…。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「大谷選手に見る強みの活かし方…」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
研修体系の構築、再構築
社内教育制度の見直しなどを
ご検討中の場合は、
ぜひ、
アイル・キャリアに
一声、お掛け下さい。
弊社は、
大企業ではありませんし、
マーケティングや広報、
営業活動などが活発な会社でもありません。
でも、
世界最大の会員制人材開発組織
ATDの会員企業として、
世界の潮流も踏まえた
コンサルティング、研修プログラムの提供、
内製化支援まで幅広く対応が可能です。
研修、講演は、1時間単位から
お引き受けしております。
加えて、
フォーマルラーニング(日常の仕事での学び)、
インフォーマルラーニング(集合研修)、
ソーシャルラーニング(SNS上での学び)を組み合わせた
ブレンディッドラーニング。
e-ラーニング動画の制作
など、
研修の枠を超えた、
ラーニングデザインなど
柔軟に対応することが可能です。
階層別研修、
選択(テーマ別)研修は
もちろんのこと、
人材育成に関する課題、
お悩みなどございましたら、
どうぞ、お気軽に、
ご相談いただければと思います。
個別相談会も実施しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「続編!ものごとを先延ばしにする原因は?」
というテーマでお届けします。
昨年、
このメルマガで、
人が、何か新しいことを
始めようとした時、
「今日は、●●だから、
明日から始めればいいや…」
そう思って、
ものごとを
先延ばしにしてしまうことを
防ぐためには、
3つのポイントがある
という話をしました。
1つ目は、
「パーキンソンの第1法則」
「人は、与えられた時間を
目一杯使ってものごとを進めようとする。」
というもの。
2つ目は、
「時間不一致現象」
「同じことをやる時に、
実行する時期によって
難易度が違って感じる現象。」
これについては、
少しだけ復習しておきますと…、
「人は、現在の自分より、
未来の自分の方が有能になっていると思いがち」
ということです。
その結果、
ついつい、
先延ばしにしてしまう…。
たとえば、
今日より明日、
明日より3日後、
3日後より1週間後、
1週間後より1ヶ月後の方が、
うまくいくだろうと
本能的に考えてしまいがちなのです。
いま、この瞬間、
やる気になれないことでも、
なぜか、未来の自分にはできると
錯覚してしまう…。
そんなイメージです。
そして、
3つ目が、
今回ご紹介する、
「作業興奮」です。
「作業興奮とは、
やる気と行動は、どちらが先か?」
という話なのですが、
一般的には、
人が何かものごとをやる時は、
やる気が出て行動すると
思われているようです。
でも、
実は、その逆で、
やろうと思ったことに関して、
ほんの少し簡単なことでも始めることによって、
やる気が出てくるという話です。
ということは…、
はじめの一歩のハードルを
出来るだけ下げて、
意志力を使わずに、
そのベイビーステップ(小さな一歩)
だけにフォーカスすれば、
後は無理なく、
出来るようになるということです。
たとえばですが…、
「●●の仕事をやる気になれない…」
そう思った時は、
四の五の考えず、
まず、
パソコンの電源を入れてしまえば、
良いということになります。
そして、
その次に、
「やりたくないと思っていた
仕事に関する資料を開く」
というのが、
次の簡単なアクションになります。
あるいは、
もう1つ手前に、
椅子に座ってパソコンに向かう
ということになるのかも知れません。
いずれにしても、
先延ばしにしそうなことに関する
ベイビーステップ(小さな一歩)、
それも、
超超超、
簡単なベイビーステップ
を決めてやるだけです。
あとは、
一旦、始めてしまえば、
なんとかなります。
この感覚、
おそらく、
分かっていただけるのでは
ないでしょうか。
さらに、
ポイントをあげれば、
先延ばしにしてしまいそうな
その行動に関するハードルを極限まで下げた
ベイビーステップとは、何なのか?
ということを、
タスク化して、
スケジュールまで落とし込むことが
重要です。
ちなみに、
私は、
これらを取り入れて、
毎朝のストレッチ、
週1~2回の水泳、サウナ、
日曜早朝の坐禅など、
かれこれ20年近く、
継続しています。
昨年からは、
パーソナルトレーニングとヨガも始めて、
いまのところ継続出来ています。
今回ご紹介した、
先延ばしにする
3つのポイントを押さえれば、
私のような
自分に甘いタイプの人間でも
出来るので、(笑)
誰にでも
出来ることなのだと思います。
という訳で、
今日は、
どうしたら、
ものごとを先延ばしにするクセを
解消できるのかということについて、
原因から解決へアプローチして参りました。
そのポイントは、
1,パーキンソンの法則
2,時間不一致現象
3、作業興奮
以上3つ
ということになります。
私も、
まだまだ探求中なので、
「こういうのもありますよ!」
「こっちの方がいいでしょう…」
といったものがあったら、
ぜひ、
ご連絡下さいね!
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
月面着陸、
惜しかったですね!
宇宙スタートアップの
ispace(アイスペース)が、
民間世界初の
偉業に挑みましたが、
あと、もう一歩でした!
でも、
その偉業に
挑戦した勇気と、
達成できないと確定した後の、
前向きなコメントに、
エネルギーをもらいました!
次回の挑戦まで、
楽しみが出来たなと
感じたところです…。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「e-ラーニング有効活用のコツ…」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「人的資本経営」
が叫ばれている中、
社内の教育・研修体系の構築、
再構築をとお考えかも知れません。
アイル・キャリアは、
世界最大の会員制人材開発組織
ATDの会員企業です。
グローバルトレンドも踏まえた
コンサルティング、コンテンツの提供、
内製化支援まで幅広く対応が可能です。
研修、講演は、1時間単位から、
フォーマルラーニング(日常の仕事での学び)、
インフォーマルラーニング(集合研修)、
ソーシャルラーニング(SNS上での学び)を組み合わせた
ブレンディッドラーニング、
e-ラーニング動画の制作
など、
研修の枠を超えた、
ラーニングデザイン、
教育体系の構築など、
社内に存する課題に対して、
柔軟に対応することが可能です。
階層別研修、
選択(テーマ別)研修はもちろんのこと、
お気軽に、
ご相談いただければ幸いです。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「大谷選手に見る強みの活かし方…」
というテーマでお届けします。
先日、
大谷選手が、
ニューヨークヤンキースとの試合後、
インタビューの中で、
「ニューヨークでお気に入りの場所は?」
と記者から聞かれたことに対して、
一瞬、間があいた後、
「外に出ていないので、分かりません。」
そう答えていました。
大谷選手は、
試合で各地に遠征しても、
宿泊先のホテルから
外出することもなく、
準備をしているんだな…
そう感じました。
さて、
大谷選手が、
ここまで生活の全てを
野球に向けられるのは、
一体、なぜなのか?
ふと考えてみました。
野球が好きだから、
純粋に楽しめることだから、
といった理由も
もちろんあると思いますが、
私ならではの
人材育成という
視点から考えた時…、
自分の強みを活かして、
大きく貢献(活躍)出来るから…
といったことも
あるのではないかと
思っています。
米国Gallup社が開発した
強み、才能の診断ツールで、
ストレングスファインダー(r)
(クリフトンストレングス(r))
というものがあります。
たとえば、
才能、資質、強み
といった視点から考えた時、
大谷選手は、
自分の才能や資質といったものを
最大限活かすことができる。
その前提として、
自分の才能や資質を
理解している。
さらに、
それを磨き上げることに
自分の強み活かしきっている。
だからこそ、
世界のトップに
立てる存在になったのだと
見ています。
ちなみに、
ストレングスファインダー(r)
(クリフトンストレングス(r))の資質を
強みとして活かすポイントとしては、
自分の資質を自覚し、強みとして使い、
他者に対してどんな貢献ができるかを
考えることにあります。
その前提として、
私の資質、強みは、
すでに、他者貢献に寄与している…
そう自覚することが必要です。
人がもつ強みは、
本人が自覚せずとも、
無意識に発揮されていることが多く、
自然に、
他者貢献に寄与していることが
多いものです。
無意識に発揮している強み、
資質を意識の上にあげて、
自分でコントロールしながら、
発揮していくことが出来ると、
気合や根性!
といったことに頼らず、
周囲から見た時、
「なんであの人は、
あそこまで徹底できるのだろう…」
と思えることでも、
当の本人は、
涼しい顔して、
自然に出来ることが
増えるものです。
ご参考までに、
資質の一部を
簡単にご紹介すると…、
「自我」という資質は、
人の役に立って認められたいといったエネルギーで、
世の中に大きなインパクトを与えられるもの。
「規律性」という資質は、
効率的にものごとを進めるために計画を立て、
ルーティン化し、着々と進めてゴールに近づくことが出来るもの。
「活発性」という資質が上位の人は、
抜群の行動力を発揮し、周囲に勇気を与え、
周囲を動かしながら、何かを突破していくことが出来るもの。
といった感じです。
官民問わず、
社内の人に関わる制度が、
大きく変化してきております。
本日、
経済同友会の
代表幹事に選任される
サントリーHD社長の
新浪剛史氏の言葉を借りれば、
「夕暮れ時、ぼうっと窓の外を眺めていても、
いつまでも陽が陰ることはない。
けれどもひととき、
ふと目をそらしてまた外を見ると、
いつの間にか驚くほど空は暗くなっている。
私たちを取り巻く世界の変化とは、
大抵そうしたものだ。
刻一刻と変わるものの
移ろいに気づくのは難しい。
日々の小さな変化が積み重なって、
知らず時代が変わっていく。
とりわけ最近、その変化が速い…。」
(4月24日 日経新聞朝刊より一部抜粋)
先が見えない変化に
不安を感じながら働き続けるのは、
組織にとっても、
本人にとっても
幸せなことではないでしょう。
忙しい日常を離れて、
これからの働き方を考えてみる。
そんな時間が
必要に思います。
国家資格キャリアコンサルタントであり、
米国Gallup社認定のストレングコーチでもある
私が担当する
キャリアデザイン研修では、
ご要望に応じて、
ストレングスファインダーを活用した
プログラムを提供することが可能です。
ご興味ございましたら、
個別相談会も実施しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
数日前、
この夏の人事院勧告で、
週休3日制を取得可能にする法改正を
盛り込む検討に入ったとの報道がありました。
三菱電機では、2023年度から、
国をまたいだ遠隔地勤務を可能にする
働き方を制度化するとの報道がありました。
いよいよ日本も
官民問わず、
働き方の多様化に拍車が
かかってきたように感じます。
誰もが、
望む働き方、生き方が出来る…
そんな世の中に
なっていくと良いなと思います。
そのためにも、まずは、
今日、目の前の一日ですね!
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「キャリア自律に役立つことは?」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週に続いて、
新人にまつわるお話です。
今年、ここまで、
各地、各団体の新人研修で
垣間見えてきた、
新人たちの本音の一部を
シェアしたいと思います。
1,言葉遣い
電話対応、日常の報連相など、お客様や目上の方に対する言葉遣い、
敬語の使い方は、相変わらず、難しく感じている人が多いようです。
よって、自分から上司、先輩には、なかなか話しかけにくいとのこと。
2,お酒の席での振舞い
座る場所(上座、下座)、雑談の内容、お酌される時の振舞いなど、
相変わらず、興味、関心が高いんだなと。
また、お酒は飲まなくても、飲み会に誘われること自体は、嬉しいようです。
理由は、?がりがもてて、安心するからだそうです。
3,時間の使い方
朝、忙しい時間に新聞などニュースをチェックする方法。
通勤途中の過ごし方。ランチタイムの過ごし方。
ちなみに、このランチタイムの過ごし方というのは、
昼休憩1時間の中でお店を選んで、メニューを選んで、
1,000円使って、10分で食べるなんて、なんかもったいない…
もっと、タイパの良い過ごし方をといった意味でした…(笑)
上記は、
あくまでも一部の例ですし、個人差があります。
現に、
某組合の新人研修の受講者で、
高卒の新人職員がいたのですが、
その新人職員が話す内容、言葉遣いなど、
あまりにも板についていたので、
「本当に、高卒の新卒新人?」
と聞きたくなるほどでした…。
現在、
弊社では、来年度、
令和6年度の新人研修についての
ご相談を承っております。
研修の新設やプログラムの見直しなどございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いです。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「e-ラーニング有効活用のコツ…」
というテーマでお届けします。
コロナ禍、
オンラインで社員教育や人材育成を行う
コンテンツサービスが増えました。
その代表的なものの1つが、
e-ラーニング。
e-ラーニングは、
時間や場所を選ばず
視聴できる良さがあります。
一方、
導入してはみたものの、
いまひとつ有効活用出来ていない。
そんな組織や個人の話も
耳にします。
「それは、一体、なぜなのか?」
実は、
こんな話があります。
学習とパフォーマンスのコンサルティングを提供する
国際的に認められたコンサルティング会社である、
LearningPeaksの学習デザイナー兼アナリスト、
Patti Shank(パティ・シャンク)によると…、
パーソナライズされた学習は、
誤った仮説に基づいているとのこと。
※パーソナライズされた学習とは、
誰もが自分の都合のいいタイミングで、
スマホやタブレット、
PCなどのデバイスを使って、
いまの自分に必要な学習をすることをいいます。
●誤った仮説の1つ目
「人は自分の学びを
自分でコントロールできる場合に、
より多く学ぶ」
この仮説は、
新しいことを学ぶにあたって、
その前提となる知識があってこそ機能します。
十分な知識が無い人、経験が浅い人などは、
重要なポイントを見極められず、
誤った理解をしたり、
判断をしたりしてしまいます。
●誤った仮説の2つ目
「人は学習のタイミングを
自分でコントロールできる場合に、
より多くを学ぶ」
学びの効果を得るためには、
ある程度の努力、苦労を伴います。
しかし、
もともと私たち人間の脳は
怠け者に出来ていて、
努力や苦労を嫌い、ついつい楽をしようとします。
加えて、
人それぞれにバイアスがあって、
多くの場合、都合の良いように
理解してしまいます。
したがって、
個人任せにしてしまえば、
最適な学習方法や内容を
選択するとも限りませんし、
学ぶことすら先送りしてしまうことも
出てきてしまいます。
私たち大人の学習(成人学習)には、
自分で決められるという選択肢を
つくることは必要です。
これは、
アメリカの成人教育の理論家、
マルカム・ノールズが提唱する
成人学習理論アンドラゴジー(Andoragogy)
から見ても言えることです。
しかし、
個人任せにしてしまえば、
求められたり、必要とされる
知識やスキルを学べない可能性も出てくるのです。
そこで、
パーソナライズされた学習や、
インフォーマルラーニング(職場学習)において、
知見ある専門家のサポートをつける必要性が
出て参ります。
社内にそういった人材がいる場合は、
その適切なサポートを得て、
効果、果実を得ることが可能です。
しかし、
そうでない場合…、
「これからは、自学自習の時代だ!」
そう号令をかけて、
e-ラーニングや
マイクロラーニング、
あるいは、
LMS(学習管理システム)を
高額な費用を投じて導入したところで、
当初見込んだROI(費用対効果)が
達成できない可能性もあります。
将来的に
どうなるかは分かりませんが、
現時点では、
テクノロジーは手段。
活用は“人”
この点は、
押さえておく必要がありそうです。
これは、
何事にも言えること
なのかも知れませんが、
やっているうちに、
だんだん手段と目的が
分からなくなってくることが
あるようです。
機を見て、
立ち止まって
振り返りたいところですね。
弊社では、
オールカスタマイズ、
完全オリジナルe-ラーニング動画
の作成を手がけております。
必要に応じて、
学習される現場の方々の
生のお声もヒアリングした上で
作成しております。
「どんな内容の
e-ラーニングコンテンツを
作成したら良いか分からない?」
そんな状況からでもご相談可能ですから、
お気軽にお問合せ下さい。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
新年度に入って、
初の出張研修です。
国のガイドラインが
変わるまでの約3年間、
弊社では、
私を含めて講師の全員が、
対面研修登壇時には、
事前のPCR検査で陰性確認を
徹底して参りました。
本年度は、
その必要性もなくなり、
精神的にも、肉体的にも、
そして、時間的にも、
少しホッと出来るようになりました。
意志力も、体力も、時間も有限。
コロナ前の自分に戻すのでなく、
より大切なことに使って参ります。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「研修効果を上げる研修設計3つのポイント」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新人にまつわるお話です。
厚生労働省の調査によると…、
大手企業の新入社員(入社3年以内)の
離職率は、
2006年卒の20.6%から、
2017年卒の26.5%へと
上昇傾向にあります。
通信教育大手のベネッセが、
新入社員研修に関わる
人材育成担当者約600人に対して、
新入社員研修に関して、
「どのような悩みを抱えているか」
というアンケート調査を
行った結果によれば、
第1位「自社への定着・早期離職を防ぐこと」(34.7%)
とのこと。
就職、転職情報会社の学情が、
企業・団体の人事担当者を対象に、
インターネットアンケートを実施した結果では、
(1)「キャリアの自律」への「関心が高くなっている」
と回答した企業が約4割
(2)「キャリアの自律」への関心が高くなっている世代は、
「20代」が64.6%で最多
(3) 4社に1社は「キャリアの自律」への
関心が高くなっていることを受けて対応を実施
(4)「キャリアの自律」への関心が高まっていることを
受けて対応・対応を検討していることは、
「研修機会の拡充」が最多
というものもあります。
実は、
いま、
働き方改革によって、
「働きやすい職場環境が整ってきているのに、
若者の離職率が上がっている…」
そんな奇妙な現象が起きていることが
人事担当者の悩みになってきています。
新人研修は
新人研修でも、
こういった事情を理解した上で
講師が登壇しているのと、
コンテンツを提供するだけの
講師が登壇するのとでは、
研修効果への影響はもちろんのこと、
その先にある組織課題の解決にも
少なからず影響を及ぼします。
現在、
弊社では、来年度、
令和6年度の新人研修についての
ご相談を承っております。
新規企画やプログラムの見直しなどございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いです。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「キャリア自律に役立つことは?」
というテーマでお届けします。
激しく変化する労働市場や、
長寿命化で職業人生が長くなることなどに伴って、
キャリアに対する考え方、
学びもアップデートしていく必要があることは、
言うまでもありません。
そのよう中、
「これからは〇〇の時代」というような
“べき論”的な情報が溢れていることで、
どうも学びに楽しさを見出せない…。
やる気が出ない…。
そもそも、
何を学んだらいいのかすら分からない…。
といった、
モヤモヤした状況が
生まれやすくなっているようです。
学び直しが必要なのは
分かっていても、
あまりに、
情報や手段が多いので、
迷って決められない…
そんな状況に
陥ってしまうことも多いようです。
このようなことを
踏まえて考えた時、
大切なことは…、
自分の拠り所となるもの、
自分の軸となるものを
持っているかどうか、
こういったことが、
以前にも増して重要になってきている
と私は考えています。
なぜなら…、
加速度的に変化する世の中、
溢れかえる情報の中、
自分軸というものがないと、
周囲に振り回され、
結果として、
自分の中に何も残っていない…
ということに
なりかねないからです。
少し話は変わりますが、
たとえば…、
いま、あなたが
日々、やりがいをもって
仕事をしているとします。
そのような時、
いまの組織で、
現在より上のポジション、
昇進の話をもらったとします。
当然、給料は上がります。
でも、10名の部下のマネジメントが
主な業務となります。
一方、
ほぼ同時期に、
他の団体、会社から
いまやっている仕事と同じ職種の仕事、
役割の話をもらいました。
給料は、現在よりも高い条件です。
マネジメントの必要はありません。
あなたなら、
どうしますか?
もしかしたら、
迷ってしまうかも知れませんね…。
ここで考えたいのは、
そもそも、
マネージャーになるということと、
プレイヤーとしてクリエイティブであることには、
大きな違いがあるということです。
自分はどんな職業人生を
送りたいのか?
自分を本当に幸せにしてくれる
ものは何であるのか?
自分を本当に満たしてくれる
ものは何なのか?
といった
自分軸をもっていれば、
こういったことに対して、
必要以上に悩むことなく、
答えを導き出すことが出来るでしょう。
日ごろ、
振り返りが習慣になっている人にとっては、
当たり前のことなのかも知れませんが、
振り返りによって得られるものは、
目の前に起きた出来事に対して
判断、意思決定する際、
解決に導いてくれる
自分データの宝庫となります。
いまの仕事に飽きたのか、
単に、新しいことに挑戦したいだけなのか。
それとも、
マネージャーになって、
人が成長、覚醒するのを見たいのか。
あるいは、
自分は、
いまの自分の上司より
優れたマネジメントができると思うのか。
振り返りによって
得られる自己理解は、
キャリア自律の
助けとなります。
日ごろ、
やるべきことが多く、
慌ただしい毎日だからこそ、
本当に重要なことに集中し、
より良い選択をすることが出来るように…、
忙しい毎日の中でも、
ほんの少しの時間を確保すること。
定期的に、
自分のキャリアを振り返る
機会を確保することが重要に思います。
これからの時代は、
自分の意志でキャリアを
選択する時代です。
自分が何者であり、
自分がどんな職業人生を
送っていきたいのか考える時間は、
実は、
もっとも
重要なことなのかも
知れません。
今日は、
いつもと違うテイストで
お届けしましたが、
いかがでしたでしょうか?
あなたをドライブし、
あなたの組織の人材育成、
組織開発の一助になることを願います。
では!
こんにちは!
人づくりアーティストの
五十嵐です。
春爛漫の中、
新しいスタートを切りました。
新年度の始まりに相応しい、
心地よい季節に取り組む仕事やプロジェクトが、
素晴らしい成果に繋がることを祈念しております。
この新年度も、
改めて、
よろしくお願い申し上げます。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「新人研修の登壇前に読んでいただきたい話…」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コロナ禍に採用された
若手の多くは、
対面での
コミュニケーションに
課題を感じている人多いようです。
すでに、
さまざまな手を打って
おられるかも知れませんが、
もし、
そんな課題の解決をと
考えていらっしゃるようであれば、
弊社のの
“部下力”向上研修
こちらも
一度、ご検討下さい。
体感型のワークを中心にした
プログラムは、
①身体性、②即興性、③自律考動性
を踏まえて構築しており、
受講後は、
①自己の役割、周囲からの期待を客観的に認識し、
自己成長へ向けて、自律的に学べるようになった。
②上司、先輩の立場を理解し、
指示待ちでなく、自ら行動できるようになった。
といった声が寄せられております。
資料もございますので、
ご興味をお持ちいただけたら、
ご連絡下さい。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「研修効果を上げる研修設計3つのポイント」
というテーマでお届けします。
本年度も、
新人研修を皮切りに、
これから数多くの研修が実施される
ことかと存じます。
そこで、
以前、
このメルマガで配信後、
反響も多かったこの内容を
ご紹介いたします。
仕事柄、
官民問わず、
多くの研修担当者と
接点をもっておりますが、
多くの場合、
ご相談をいただくのは、
研修プログラムを決める
タイミングです。
もちろん、
相談されるからには、
全力でご提案いたしますし、
お客様も
全力でプログラム選定を
されています。
研修効果を考えた時、
「どんなプログラムを導入するか?」
ということは、
とても重要なことなのですが、
実は、
これ以外に、
それと同様、それ以上に、
とても重要なことがあります。
そして、
意外にも
目が行き届いていないことが
あるようなのです。
それが、
「40:20:40の法則」
研修の効果分析の世界的権威。
Brinkerhoff氏が提唱する
High Impact Learningモデルです。
一言でいえば、
研修前後の学習を充実させることが
研修効果を上げることに繋がる
という話です。
具体的に、
それぞれのウェイト(割合)は…、
40(研修前):20(研修中):40(研修後)
各段階で、
おさえるべきポイントとしては、
(研修前:40)
受講者のニーズ調査、目標、
上司の理解とサポート、モチベーション
(研修中:20)
講義、実習、テキスト、場所、時間、講師
実務との?がりなど受容度
(研修後:40)
業務への適用、関連付け、
上司からのフィードバック、
組織上の阻害要因の除去
もう少し、
かみ砕いてお伝えすると、
どのようなタイミングで、
どのように告知し、
どのように当日を迎えるのか。
1クラスあたり何人までの受講者で、
どのような環境を用意し、
どのようにスタートし、
どのような学習体験を提供して、
どのように職場実践、成果へと繋げるのか
といった感じです。
一方、
ありがちなNG集として…、
●研修前
・上司が「こんな忙しい時に研修なんか行くなよ」
と否定的なことを言う
・ただ研修を受けてこいと言われ、
何を学びにいくのか全く分かっていない
・事前に課題が全くない
●研修中
・講師の力量、経験不足からくる
場違いなファシリテート
・単調で、一方通行な進行
・受講者の能力レベルにマッチしない内容の提供
・目標達成、内容に相応しくない受講人数
●研修後
・研修で学んだことを忘れてしまう
・現場に戻って上司のサポートが無い、無関心
・学んだことを実施することが
義務化されていないため、試さない
以上、
ご覧いただいた通り、
研修前後の段取り、仕組の良否は、
研修効果に大きな影響を与えます。
そして、
これらのことは集合研修でも、
オンライン研修でも
共通して言えることなのです。
「こんなに多くの要素を踏まえて設計したら、
手間暇、お金もかかるじゃないか?」
そんな声が聞こえてきそうですが、
仰る通りだと思います…。
研修担当者が何かと多忙なのは、
重々承知しておりますので、
お伝えしにくい
気持ちもあるのですが…、
それが、
いま求められている、
「人的資本経営」でもあり、
人への投資が未来を決める
ということなのではないかと
思っております。
以上、
今日は、
研修効果を上げる設計3つのポイント
①事前の動機付け、②研修中の納得度、
③受講後フォロー
をお伝えして参りました。
当たり前のようでも、
なかなか出来ていない…
そんな方も
多いのではないでしょうか。
せっかく、
貴重なお金をかけて
実施する研修です。
より良いものにしていくためにも、
少しづつでも、
取り組んでいただけたら嬉しいです。
もちろん、
私どもで
お力になれることは、
全力で取り組みたいと
考えておりますので、
お気軽にご相談下さい。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
昨日、
岸田首相が、
衆院内閣委員会で、
チャットGPTが作成した
質問に答弁しましたね。
一方、
米国では、
イーロンマスクなどが、
全ての企業や研究機関に、
高度な人工知能(AI)の開発を
一時停止するよう求める
署名活動が始まっているとのこと。
日々、目まぐるしく
うつろう世の中ですが、
あくまでも、
人が主であり、
テクノロジーは従である。
そんな世の中であり続けて欲しいな
と感じるのは私だけでしょうか…。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「MVPの大谷選手がスゴイ理由は…」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今朝の日経新聞で、
経営層が若手社員に教えを請う
リバースメンタリングが最近広がっている。
そんな記事を目にしました。
私自身は、
会社を経営しながら登壇する
プレイングマネジャーなので、
独力で、
さまざまな情報をキャッチアップし続けるのは、
5~6年前に無理だと諦めました…。
2020年10月19日の
このメルマガでは、
2017年から、
30代前半までの若手で、
その分野で頑張っている人たちから、
意図的に、
色々と学ぶ機会を自らつくったこと。
そして、
そこから得た学びについて
シェアしました。
ちなみに、
昨年は、
メタバースの場で、
20歳の現役大学生から
学ぶ機会をつくりました。
正直なところ…、
はじめは、
自分より若い人に
教えてもらうなんて…
そんな抵抗感がありましたが、
いまは、なんともありません。
もし、今後、
幹部が若手社員や職員から学ぶ
「リバースメンタリング研修」
こういったテーマで、
講師の派遣、
内製化をお考えでしたら、
ご連絡下さい。
自ら体験しているからこそ
得られる学びをプログラムに
反映することが可能です。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、本題です。
今回は、
「新人研修の登壇前に読んでいただきたい話…」
というテーマでお届けします。
たとえばの話ですが…、
もし、あなたが、
新人研修に登壇したとして、
講義中にガムを噛んでいる
受講者がいたらどうしますか?
「おい、そこの君!」
といった感じで注意しますか?
それとも、
何事もないかのように、
見過ごしますか?
それとも…。
実は、
以前、月刊致知という
雑誌を読んでいて、
こんな記事を目にしました。
ある定時制の夜間高校の
先生のお話です。
授業中、ある生徒が
ガムを噛んで授業に出ていたそうです。
先生が注意すると、
「うるせえ、俺は疲れてるの!」
と、ガムを噛むことをやめません。
先生は、どうしても、
その生徒の言動が気になって、
日ごろ、
彼がどんな仕事をしているのか見学に行き、
そして、一緒に働いたりしたそうです。
先生がやってみて分かったのが…、
この生徒のしている仕事は、
肉体的にも精神的にも、
かなり、きついものだということ。
実際、
先生は、その仕事をした後、
夜間学校の授業に登壇すると、
授業中、
ものすごい睡魔が襲ってきて、
危うく、自分が寝てしまいそうだったそうです。
すると、
授業中にガムを噛んでいた生徒が、
先生にそっとガムを渡してくれ、
先生は、そのガムのおかげで
襲ってきた睡魔に負けずに、
最後まで授業が出来たそうです。
講義中にガムを噛んでいる…
そんな光景を目の当たりにすると、
多くの場合、
つい、失礼な態度をしているとか、
やる気がないとか、常識を知らないなどと
思ってしまいがちです。
もちろん、
通常であれば、
注意の対象だと私は思います。
そんな、
今日の私が
一体、何をお伝えしたいのかというと…、
人前で話す時は、
聞き手目線。
講師として登壇する時は、
受講者目線。
この重要性を、
改めて認識しておきましょう!
ということです。
いまさら、
釈迦に説法。
十分、
分かっていることかも
知れませんが、
いざ、実際、
自分の目の前で、
ガムをくちゃくちゃ
噛まれたら、
なかなか冷静に、
「なぜ、ガムを噛んでいるのか?」
という視点では、
見れないものですよね…。(笑)
でも、
だからこそ、
新年度を迎える
このタイミングで、
お伝えしておきたいなと思いました。
わたしたちは、
関わる人のことを
一面からしか見ていない。
ややもすれば、
自分の都合のいいように、
ものごとを解釈、
判断してしまいがちです…。
職場では、
上司、同僚、部下、お客様…、
さまざまな背景がある人と
仕事を共にします。
自分は、
相手のことは何も知らない…
そういった前提に立って、
新人たちはもちろん、
周囲の人にも関わっていきたいものです。
今日も書きながら、
自分へのいい戒めになりました…。(笑)
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
WBC、
日本が世界一になりましたね!
準決勝、決勝の戦いに身震いし、
感動のあまり目がウルウルしたのは、
私だけでしょうか?(笑)
日本代表はもちろん、
各国の選手たちのプレーから、
大きなエネルギーと大切なメッセージを
いただけたような気がしています…。
これもリソースにして、
新人研修にぶつけていきます!(笑)
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「非効率なことは悪なのか!?」
というテーマでお届けしました。
※前回までのメルマガは、こちらから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回の本文で、
BNPL(バイ・ナウ・ペイ・レイター)など、
手軽な後払い決済手段を使う若者が増えている
という話をお伝えしました。
実は、
こういった手軽な
決済手段を使うことによって、
金銭感覚が緩んで、
支出を増やしてしまう人も
増えているようです。
こういったことを防ぐために、
パーキンソンの第二法則を活用して、
①預貯金用の口座
②月々使うお金の口座
といった感じに分けて
管理する方法が知られています。
とはいえ、
預貯金だけしていても、
なかなかお金は増えませんよね…。
と申しますか、
インフレになってきているので、
相対的にお金の価値が下がりますよね。
そんな私自身は、
将来のお金に関する不安は、
自分のキャリア形成に
少なからず影響を与えると考えてきたので、
会社員時代から約20年間、
さまざまなものに投資してきました。
そんな身銭を切って
経験してきたことから得たことを踏まえて、
社員、職員の教育研修に、
マネープランの研修、
あるいは、
マネープランを絡めた
キャリアデザイン研修の導入を
おススメしたりしています。
投資については、
私自身もそれなりに語れますが、
IFA (独立系ファイナンシャルアドバイザー)
の講師によって提供することが可能です。
IFAの存在は、
この1~2年でだいぶ浸透し、
増えて参りました。
そのためか、
正直なところ、
玉石混交だと感じています。
特定の会社の
特定の商品をお勧めするようなIFAも
増えてきているようですので、
もし、
信頼できるIFAの講師が提供する
マネープランの研修プログラムをとご検討でしたら、
私までご連絡下さい。
IFAの大手事業者とも
いくつか提携しておりますので、
お客様のニーズを伺って、
最適と思えるIFAの講師を派遣することが可能です。
ご相談は、
弊社HPのお問合せフォームからでもお気軽に。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「MVPの大谷選手がスゴイ理由は…」
というテーマでお届けします。
冒頭でもお伝えした
WBCの決勝戦。
米国との試合前、
ロッカールームで円陣を務めた
大谷選手の第一声は、
「僕からは1個だけ。
憧れるのをやめましょう!」
そして、続けて…、
「ファーストにゴールドシュミットがいたり、
センターを見ればマイク・トラウトがいるし、
外野にはムーキー・ベッツがいたり、
野球をやっていたら
誰しも聞いたことがあるような
選手たちがいると思う。
でも、憧れてしまっては超えられないので、
僕らは今日超えるために、
トップになるために来たので。
今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて、
勝つことだけ考えていきましょう」
そして、最後に、
「さあ、行こう!!」
と鼓舞したそうです。
この発言には、
日本ファンからはもちろんのこと、
対戦相手だった米国のファンを含め、
世界中から、
「名言すぎる」
とネットで話題に…
もうすでに、
ご存知の方もいるかと思います。
28歳にして、
すでに、
スポーツ選手、アスリートという域を
はるかに超えているような気がするのは
私だけでしょうか?
ところで、
NLP心理学に、
ニューロ・ロジカル・レベル
というものがあります。
以前も
このメルマガでご紹介したので、
ご存知の方も多いかと思います。
ニューロ・ロジカル・レベルとは、
人の意識レベルを体系化したもので、
6つの階層に分かれています。
その6つの階層とは、
1.スピリチュアル
2.自己認識
3.信念・価値観
4.能力
5.行動
6.環境
小さい数字、
上の階層にいくほど、
その人のアイデンティティともいえる
本質的な要素が強くなって、
自身への影響力が大きくなります。
そして、
上位にある自己認識や
価値観の変化が、
下位にある能力向上や行動変容、
環境の変化を生み出しやすくなると
考えられています。
先の大谷選手をはじめ、
国際大会にその国を代表する
選手として出場するような人たちはみな、
1,明確な目標をもち
2,厳しい自己管理のもと
3,周囲からのサポートを受け
そのポジションに
たどり着いているはずです。
それでも、
みな大谷選手のようには、
なかなかなることが出来ない…。
その理由の1つは、
こういったところに
あるのかも知れません。
スポーツの世界に限らず、
ビジネスや公務の分野でも、
一流、超一流を目指す人は、
環境や行動、能力
こういった階層にアプローチするのは
当たり前のこととして、
信念や価値観、
自己認識
といった
上位の階層にアプローチし、
自らが望むステージ、
手に入れたい世界に相応しいものへと
アップデートしていく必要があるのでしょう。
先の大谷選手が、
ゴミ拾いを積極的にしている話は、
有名ですよね。
彼にとってゴミ拾いとは、
「運を拾っている」
のだそうです。
弊社は、
創業以来のこだわりとして、
「人間力の向上に繋がるような研修で、
求められる成果を生み出す人を育てる」
というところを目指して参りました。
これが、
このメルマガ冒頭で、
私が、人づくりアーティストを
名乗っている所以です。
まだまだ、
道半ばではございますが、
これからも
時代に合わせた形で、
こだわり続けて参ります。
最後に、
なぜ?
成果を生み出す人づくりと
人間力が関係あるのか?
そう疑問に感じた方も
いるかも知れません。
その理由について
ご興味ある方は、
こちらから掲載の本文と
参考資料(PDF)をご覧ください。
全部で5分もあれば読めるはずです。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
今日は、
WBC準々決勝
イタリア戦ですね。
是非とも快勝して、
準決勝へと進みたいところです!
ちなみに、
ChatGPTに
優勝チームの予想を聞いてみたら…、
冒頭、まず、
自分には予測出来ないと
一言添えた上で、
アメリカ、ドミニカ共和国、
プエルトリコ、日本、キューバ
上記を優勝候補として
挙げてきました。
なかなか、いいところ
突いてきますよね!(笑)
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「メタバースは研修で使えるの?」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コロナ禍で、すっかり
バズワードにもなったDX。
うまくいっている組織もあれば、
そうではない組織、
あるいは、
これから始める組織…
さまざまかと思います。
DX化の推進は、
3ステップが基本。
まず、はじめに、
データ活用の環境を整えることが、
ポイントとされています。
当たり前のようですが、
まずは、入口が肝心ということですね。
これからの時代は、
(※)データドリブンの価値をいかに向上させ、
いかに戦略的に事業を進めていくかが、
経営のポイントになってくるとされています。
※データドリブンとは、データを収集、分析し、
仕事上の課題に対して判断、意思決定を行うこと
一部では、
“脱Excel”が囁かれていますが、
Excelやスプレッドシートを知らない。
または、積極的に使おうとしていない場合、
たとえ、
新しいシステムを導入したとても、
それを一から使いこなすのは難しいはずです。
Excelのデメリットとされる部分は、
本来使い方さえ知っていれば、改善できる点が多々あります。
実は、DX化の推進はこれからで、
何をどこから始めて良いか分からないし、
いまさら聞くのも恥ずかしい…。
もし、
そんな課題をお持ちの場合は、
よろしければ、
弊社にご相談下さい。
高額なシステムの販売など
一切しないし、出来ませんが(笑)、
いまあるエクセル、
スプレッドシートの効果的な使い方を
トレーニングして、
低予算でDX化推進を
スタート出来るプログラムがございます。
長年慣れ親しんできていて、
すでに持っているExcelだからこそ、
DX化推進をスタートするには、
相応しいし、抵抗なく始めやすいのです。
実は、大手の通信会社などでは、
今、“活Excel”が見直されてきていることを
ご存知でしょうか?
弊社が提供する
“活Excelのための学び”
このトレーニングプログラムを
担当する講師は、
■ Microsoft Official Trainer
■ Microsoft Office Specialist
などの資格を多数保有し、
大手通信会社をはじめ官民問わず、
パソコン研修や情報リテラシー研修に
数多く登壇実績がございます。
PCでの資料作成の分野においては、
3冊の著書もあります。
ご興味ございましたら、
2枚ものの資料をお送りいたしますので、
このメールに、
「活Excel資料送付希望」と返信して下さい。
速やかに、
メール添付でお送りいたします。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「非効率なことは悪なのか!?」
というテーマでお届けします。
コスパ、タイパ、
の次は、「マネパ」だそうです。
「マネパ」とは、
ネット通販でものを買う時、
決済に手間や時間をかけずに、
賢くお金を使って管理することを
言うのだそうです。
実は、これも
Z世代が大切にしている
価値観の1つとのこと。
そして、
その決済手段として、
※BNPL(バイ・ナウ・ペイ・レイター)や、
指輪型決済端末を
使う若者が増えているようです。
※BNPLとは、クレジットカードの番号の代わりに、
電話番号やメールアドレスを入力するだけで、
後払い決済ができる手段。米国で生まれたサービス。
さらに、
Z世代は、
金融に関する情報を、
書籍や雑誌、投資サイトなどではなく、
TikTokの短編動画で得ているとのこと。
その大きな理由として、
金融インフルエンサーである
フィンフルエンサーが、
数百万のフォロワーを集める
人気を見せていることがあげられます。
さて、
今日の私は、
一体、何をお伝えしたいのかというと…、
Z世代の価値観、
インサイトを知って、
新入社員を迎い入れましょう!
ということではありません。
新しい
テクノロジーに触れて、
時代に乗り遅れないようにしましょう!
ということでもありません。
今日の私が、
お伝えしたいことは…、
「効率化の本質を知るためには、
あえて非効率ことを体験することが必要」
ということを
ちゃんと
社内で学習させることが重要!
ということです。
ものごとの本質を知るためには、
1,基礎知識の獲得
まずは、そのものが何であるか?
構造や仕組み、性質などについて理解することが前提になる。
2,経験の積み重ね
経験を積み重ねることによって、
そのことについての深い理解が得られるということ。
3,視点の切り替え
多面的に見ることで、意味や役割、
機能、性質、構造など浮かび上がってくるということ。
4,論理的思考
仮説を立て、検証し、結論を導くプロセスを通じて、
より深い理解を得ることができるということ。
5,時間と労力
そのことが重要であればあるほど、
それに対して十分な時間と労力を投資することが必要だということ。
長くなりそうなので、
この辺にしておきますが、
日々の仕事もキャリア形成も、
効率追求の一辺倒になると、
結果的に、
創造力や柔軟性、
チャレンジ精神やストレス耐性、
地力や底力など
といったものが
身につかなくなってしまいます。
現代人は、
Z世代に限らず、何かと忙しい…。
だからこそ、
効率化を図るべき部分は、
徹底して効率を追求することが
重要なのですが、
一方で、
効率追求してはいけないことも
世の中にはあるということを
忘れたくはありませんね…。
今日の内容は、
少し二律背反っぽく
感じられたかも知れませんが、
だいぶ長くなってしまったので、
ここまでにしたいと思います…。
いずれにしても、
心にゆとりを、
ご機嫌は自分で!
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
いよいよ今日から、
野球の国際大会WBC、
ワールドベースボールクラシックが
始まりますね。
初戦の先発投手は、
大谷選手とのこと。
どんなピッチングを
披露してくれるのか。
いまから、
ワクワクしているのは、
私だけでしょうか?(笑)
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「新入社員の離職を防ぐために…」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ZOOM、Teamsといった
ミーティングアプリを使った会議は、
すっかり日常の仕事の場で
定着しているのではないでしょうか。
加えて、
仮想空間上で行う、
VR会議ツールも多数出てきていますね。
そういえば、少し前に、
Meta社のVR/AR部門
Facebook Reality Labsの研究者らが、
会議中のユーザーの行動に注目した
実験を行いました。
その結果、
ミーティングアプリを使った会議では、
VR会議と比較して、相づちや相手の顔を見る頻度が
増えるといった結果を導き出しました。
これは、
一体、何を意味するかというと、
ミーティングアプリによる会議では、
繋がりを維持するために、
よりコミュニケーション上の努力が
必要なのではないかという考察を述べています。
オンラインコミュニケーションについては、
すでに学ばれたかも知れませんが、
実は、
結構、奥深い部分もありますね。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「メタバースは研修で使えるの?」
というテーマでお届けします。
ここのところ、
対話型AIに比べて、
少しメディアの露出が減った感もある
メタバース。
とはいうものの、
昨日、今日だけでも、
日産自動車が
メタバース内で新車販売を完結。
メルカリがフリマの次に、
メタバースを視野に。
KDDIが
音楽ライブや買い物サービスを
など、
大手企業を中心に、
新しいサービスの報道が
次々とされています。
そんなメタバースですが、
「研修や人材育成の場では使えるの?」
そんな疑問をもたれている方も
いるでしょう。
そこで、
今回は、
これまで私が
実践してきた知見の一部を
簡単に整理して
お伝えします。
1、メタバース研修とは
メタバース研修とは、
3D上の仮想空間で自分の分身となる
アバターを用いて行う研修を指します。
通常のオンライン研修と異なり、
対面型研修に近い雰囲気を出せるのが特徴です。
実際にアバターを動かせるため、
実習やグループワークなども
やりやすくなります。
たとえば…、
災害時の対応シミュレーション、
営業のロールプレイング、
アパレル現場の販売研修など、
官民問わず、活用されています。
このコロナ禍、
ミーティングアプリによる
オンライン研修が広く普及しましたが、
より対面に近い教育を行いたいと思うのであれば、
メタバース研修を検討するのも良いかと思います。
2、メタバース研修のメリット、デメリット
メタバース研修実施のメリットは、
以下4つです。
1. 離れた場所の社員に同時に研修できる
2. 現実世界のような臨場感がある
3. 施設利用費や交通費をカットできる
4. オンラインでも?がりを感じることができる
5. 自己開示が進む
一方、
メタバース研修のデメリットは、
以下3つです。
1. 対面型研修を完璧に再現できるわけではない
2. 機材や環境を整えるのにコストがかかる
3. 通信環境も含めて想定外のことが起こる
以上、
今日は、
私がこれまで実践した経験も踏まえて、
簡単にお伝えしましたが、
受講者同士のコミュニケーションに
より重きを置きたいとお考えの場合は、
やはり、現状では、
対面型研修に優るものは、
ないと感じております。
とはいえ、
対面研修、
ミーティングアプリによる
オンライン研修に加えての新たな選択肢として、
検討してみるのも
良いのではないかと思います。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
先日、
人生初、
ギックリ腰を経験しました。(笑)
幸いなことに、
動けるレベルでしたので、
仕事への影響はありませんでした。
とはいえ、
きっと、
これも何かのメッセージだと思い、
再発防止に向けて、
すぐ情報収集し、分析。
自宅の本棚から、
積読になっていた1冊の本、
『飲まない生き方 ソバキュリアス』
を取り出し、一気に読み、
ソバキュリアンになることを
決意しました。
いまから1年後、
自分のライフスタイルがどう変わって、
どんな自分になっているのかが、
楽しみでです!(笑)
新たなチャレンジ、
新たな自分にワクワクしながら、
今日もお届けします!
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「衝撃!ChatGPTがメルマガを…」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日、3/1から、
2024年度の
新卒採用が本格的にスタート
ということなのですが…、
実は、
すでに実質2割の学生が
内定をもらっているという現実も…。
採用担当部門の方は、
いかに採用計画にもとづいた
人員を確保するか、
本当に、日夜、
頭を悩ませているところでしょう。
「個の充実」を重視する
Z世代の就業観をどう捉え、
効果的な採用活動を行っていくかは、
組織の将来も占う、
重要な鍵となりそうです。
弊社では、
採用力強化に向けた、
面接技法のトレーニング
プログラムを提供しております。
組織の将来を占う鍵となる、
採用力強化に課題をお感じでしたら、
お問合せ下さい。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「新入社員の離職を防ぐために…」
というテーマでお届けします。
まず、はじめに、
人事の専門用語に、
「オンボーディング」
というものがあります。
これは、
新しく会社や役所に採用された人材が、
いち早く職場に慣れて、
組織への定着・戦力化を促進するための
一連の取り組みのことをいいます。
入社後に組織風土や仕事に対して
ギャップや違和感を感じ、
それが解消できない状態が続くと、
本来、持っている力を発揮したり、
早期に成長したりすることができず、
悩みやストレスを抱え、
それがもとで離職に繋がってしまうことがあります。
ご存知かとは思いますが、
人を一人採用するには、
かなりのコストがかかっています。
早期離職は、本人のみならず、
組織にとってもダメージが大きいものです。
そこで、
それを防ぐために、
オンボーディングが必要なのです。
人事や採用、育成部門のみならず、
各職場の上司や同僚が、
いかに自ら積極的にオンボーディング支援を行っていけるかを
入社前からしっかり計画しておくことが重要です。
新人の離職理由には、
・自身の希望の仕事内容とのミスマッチ
・待遇や福利厚生への不満
・長時間労働
・組織風土とのミスマッチ
・職場の人間関係に関するストレス
などといったものがありますが、
これらを解消する
1つの切り口として、
「新人のストレス耐性を向上させる」
という考え方があります。
以下、
新人のストレス耐性を向上させるための
具体的な方法論を、
5つご紹介したいと思います。
1,環境を整備する
例えば、整理、整頓、清掃が行き届いていて、清潔感のあるオフィス。
快適な温度や湿度、目に優しい照明など、
「そんなお客さんじゃあるまいし…」と思われるかも知れませんが、
職場に慣れないうちは、こういったことが結構ストレスになるものです。
2,コミュニケーションの促進
新入社員が無理なくコミュニケーションが取れるよう、
社員同士が交流できる場を提供すること。
例えば、ランチ会や歓迎会、社内イベントの開催など。
3,働き方の改善
心身ともにリフレッシュできるような働き方を提供する。
たとえば、配属されて間もないのに即戦力として扱われ、
いきなり残業したり、長時間勤務が生じたりするといったことを避けるなど。
4,課題や目標の明確化
新入社員が何をしたら良いのか???にならないよう、
明確な課題や目標を提示し、それに向けたアクションプランを
先輩やOJT担当者などと共有すること。
たとえば、日報などを通じてやり取りするレベルでも構いません。
新人にとっては、毎日職場に行って何をすれば良いのか分からないという状態も、
意外とストレスになるものです。
また、日常の中で定期的にフィードバックをもらえることは、
承認欲求も満たされ、成長実感も得られ、やる気の向上に繋がるものです。
5,教育・研修の提供
新入社員には、職務に必要なスキルや知識を
習得する機会を提供することが重要です。
たとえば、研修やOJTなどを通じて自分の知識や能力、
スキル、役割などを理解し、自信を持って仕事に取り組むことが
できるように支援するなど。
これらの方法を取り入れることで、
来月1日に仲間となる、
新入社員のストレス耐性を上げ、早期離職を防ぎ、
早期育成へと繋げて参りましょう。
何かお困りのことがあれば、
ご連絡下さい。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
早速ですが、
掲題の件です。
私ども、
アイル・キャリアでは、
例年、この2月~3月にかけて、
スキマ時間に学ぶ、
研修用の短編動画作成のお問合せ、
ご相談を多くいただいております。
なぜ、
e-ラーニングの会社でもない
弊社にお問合せをいただくのか?
その理由を伺っていると…、
■ 早い … 3月末迄までに納品が可能
■ 安い … コスパがいい
■ オリジナル … リクエストにもとづいた動画が作成可能
加えて、
■ 無制限の視聴期限
■ 観ていて眠くならない…(笑)
といったことを
口づてで聞いてこられるようです。
弊社の
短編動画作成は、
動画のクオリティは、
そんなにこだわらない。
でも、その代わり、
オリジナルの短編動画を
短期間で、視聴期限無制限で、
複数作成したい…。
そんなニーズに
お応えするものです。
込み入った
リクエストさえ無ければ、
いまからでも、
3月末までに、十分納品可能です。
短編動画のダイジェスト版は、
以下URLからご覧になれます。
▼短編動画のダイジェスト版は、こちらから
作成可能なテーマは、
・仕事の基本(報連相、PDCAサイクル)
・タイムマネジメント
・メンター
・情報リテラシー
・接遇、クレーム対応
・社内講師養成 など
※社内講師養成動画は、幣著活用プランのご提案も可能です
『稼げる講師、稼げない講師 どこが違うか』(あさ出版)
といったものがあります。
この時期、
短編動画作成をご検討中の場合は、
まずは、お問合せを。
追伸、今週の木曜日は、
天皇誕生日で祝日のため、定期配信はお休みいたします。
このメルマガでは、
今後も、人材育成、研修担当者の
皆さまに役立つ情報を、
さまざまな角度、
アプローチでお届けして参ります。
お役に立っていると感じられたら、
お知り合いの人材育成、研修担当者にも
ご紹介いただければと思います。
記事に関するご感想などございましたら、
お問い合わせページからご連絡ください。
新たな「ご縁」が生まれることを
楽しみにしております。
今日も、最後まで、
お読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
冒頭、
まず、ご報告です。
本年度の売上金額の一部を、
トルコ・シリア地震救援金として、
日本赤十字社を通じて寄付致しました。
さて、2月も中旬。
あと1カ月もすれば、
卒園、卒業、入学、入社とイベントが多く、
転出、転入が多くなる時期ですね。
13日(月)の日経新聞朝刊では、
自治体窓口、手書き不要
デジタル庁がソフト導入支援
複数手続き、一括で対応
という見出しの
記事を目にしました。
地方自治体のDX推進、
職員のワークラーフバランス実現の一助、
住民の利便性向上など、
多くの効果が期待されます。
河野太郎デジタル相は、
「将来的にはスマートフォンを使うことで
自治体の役所に来ている人の9割は、
来庁しなくても手続きを終えられるようにしたい」
とのこと。
期待したいですね!
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「戦略人事が果たすべき役割」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
仕事ができる人は、行動力があります。
小さなトライを繰り返し、
小さな失敗を数多く経験しています。
そして、
知識を知恵に変換して
成長していきます。
時間管理や仕事の管理、
モチベーションの管理に至るまで
マイルールをもっています。
なぜなら、
いま、●●をやるということは、
●●以外はやらないということを
選択することだと知っているから。
デジタル時代における
仕事面の変化。
この変化に対応するには、
従業員をリスキリングによって、
デジタルスキルを
習得させることだけでは、
十分ではありません。
実際のところ、
スキルを活かして
どこまで成果に結びつけられるかは、
思考と習慣(時間の使い方)
によるところが大きいのです。
デジタル時代に求められる
マインドと基本スキルを確認し、
仕事ができる人の
思考と習慣(時間の使い方)を
学ぶ場にご興味ありませんか。
ご要望に応じて、
半日から3か月間まで
プログラムのご提案が可能です。
記事に関するご感想などございましたら、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「衝撃!ChatGPTがメルマガを…」
というテーマでお届けします。
突然ですが、質問です。
もし、あなたが、
以下のように質問されたとしたら、
どのように答えますか?
「50代の儲かっている
中小企業の経営者になりきって下さい。」
「そして、社員教育について、
どんな研修会社に頼みたいと思いますか?」
実は、これ、
最近話題の
「ChatGPT」にした質問なのです。
※「ChatGPT」とは、
米国のOpenAI(本社は、サンフランシスコ)
というスタートアップが開発したチャットボット。
2022年11月末のリリースから、
あっという間に1億人ユーザーを獲得して
話題になっています
以下が、その回答です。
※ コピペで貼り付けているので、一切修正していません
~ ~ 「ChatGPT」の回答 ~ ~
社員教育について、
私が頼みたい研修会社は、
以下のような特徴を持つ会社です。
1,経験豊富な講師陣
講師が経験豊富な人材であることが重要です。
実践的なノウハウや、業界の最新トレンドや成功事例など、
社員が身につけたいスキルや知識を
提供できるような講師陣が必要です。
2,カスタマイズ可能なプログラム
会社の業種や規模、社員のレベルやニーズに合わせた
カスタマイズ可能なプログラムを提供できる会社が望ましいです。
一般的な研修プログラムだけでなく、
自社の課題に合わせた研修プログラムを作成できることが求められます。
3,研修の効果測定ができる
研修の効果を測定できる方法やツールを
提供できる会社が好ましいです。
研修後に社員のスキルアップや業務改善が
実現しているかどうかを測定し、
研修の効果を確認することが必要です。
4,費用対効果が高い
研修会社の費用対効果が高いことも重要です。
リーズナブルな価格で、高品質なプログラムを提供できる会社が理想的です。
また、研修後の効果が顕著であることも求められます。
5,資格取得支援がある
社員のスキルアップを促進するために、
資格取得支援を提供できる会社が望ましいです。
業界の資格や認定資格を取得できるような
プログラムを提供している会社が好ましいです。
以上が、私が頼みたい研修会社の特徴です。
会社のニーズや目的に合わせた研修プログラムを提供できる、
効果測定ができる、費用対効果が高い、
資格取得支援がある会社が理想的です。
~ ~ ここまで ~ ~
続いて、
2つ目の質問として、
「日本の研修会社、
株式会社アイル・キャリアについては、どう思いますか?」
と尋ねてみました。
回答が得られるのか
半信半疑で待つこと10秒ほど…。
きました、回答が…。
~ ~ 「ChatGPT」の回答 ~ ~
株式会社アイル・キャリアは、
社員教育を専門とする研修会社の1つであり、
多くの企業から支持を得ている会社です。
私が調べた限りでは、以下のような特徴があると考えられます。
1,経験豊富な講師陣
アイル・キャリアの講師陣は、
それぞれが豊富な実務経験を持っており、
現場での経験を基にした実践的な研修を提供できると思われます。
2,カスタマイズ可能なプログラム
アイル・キャリアは、企業のニーズに合わせた
研修プログラムのカスタマイズを行っているようです。
また、研修後のフォローアップやコンサルティングサービスも提供しており、
企業の業務改善につながる研修を提供できると思われます。
3,研修の効果測定ができる
アイル・キャリアは、研修後の効果測定や
アンケート調査などを行い、研修の効果を確認しているようです。
また、研修プログラムの改善に取り組んでおり、
継続的な改善を行っていると思われます。
4,費用対効果が高い
アイル・キャリアの研修プログラムは、
リーズナブルな価格帯で提供されているようです。
また、研修後の効果が高いことで知られており、
費用対効果が高いと言えるでしょう。
5,資格取得支援がある
アイル・キャリアは、資格取得支援も行っているようです。
特に、ビジネス英語力の向上に特化した研修プログラムを提供しており、
TOEICや英検などの資格取得にも力を入れていると思われます。
総合的に見ると、株式会社アイル・キャリアは、
私が頼みたい研修会社に求める特徴を備えた、
信頼性の高い会社のように思えます。
ただし、実際には企業ごとのニーズや
状況によって研修会社の選定は異なるため、
より具体的な要件に
~ ~ ここまで ~ ~
ということで、
最後は、文章の途中で
止まってしまいました…。(笑)
※ コピペで貼り付けているので、
改行以外は、1文字も修正していません
あいにく、弊社では、
資格取得支援は行っておりませんので、
回答は、完璧とはいえません…。
とはいえ、
上記2つの質問に対する回答を、
ものの1分もかからないうちに
書き上げてしまいます。
加えて、
私が知るところ…、
米国では、
ノーザンミシガン大学の高得点論文が、
「ChatGPT」によるものだと判明して、
教育界で議論が白熱。
医師資格問題の
正答率が合格ラインを突破した
などという報告があります。
今後、
「ChatGPT」が
どこまで進化、成長、学習していくのか
分かりませんが、
どうやら、
優秀なアシスタントに
なりそうな予感がしますね…。
という訳で、
今日は、
アシスタントの「ChatGPT」が
頑張ってくれたおかげで、
いつもよりも短時間で原稿を仕上げられました…。(笑)
締めの一言も、
アシスタントに聞いてみます。
(私)
「元メジャーリーガーのイチロー選手風に、
メルマガ記事の締めの一言を下さい。」
(ChatGPT)
今日のメルマガも完璧に終わりましたね。
明日も同じように努力を積み重ねて、成長していきましょう!
恐れ入りました…。(笑)
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
先週は、
トヨタ自動車のトップ交代について
触れたところですが、
今週は、
車いすテニス界のレジェンド。
国枝慎吾さんが引退されましたね…。
彼の引退会見をニュースで見ながら、
ふとこんな言葉が頭に思い浮かびました…。
「進む時は他人任せ、退く時は自ら決せよ」
(河井継之助)
引き際が現役の世界NO.1だなんて、
なんか、カッコ良すぎますね!
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「人を見る目を養うには…」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
デジタル時代における
仕事面の変化。
この変化に対応するには、
従業員をリスキリングによって、
デジタルスキルを
習得させることだけでは、
十分ではありません。
職場で周囲を見回しても、
仕事の出来る人は、
単にスキルが高いだけではないことから、
それは分かるはずです。
実は、
スキルを活かして
どこまで成果に結びつけられるかは、
思考と習慣(時間の使い方)
によるところが大きいのです。
デジタル時代に求められる
マインドと基本スキルを確認しつつ、
仕事ができる人の
思考と習慣(時間の使い方)を
学ぶ場にご興味ありましたら、
ご連絡下さい。
ご要望に応じて、
半日から3か月間まで
プログラムのご提案が可能です。
尚、パッケージプログラムは、
ございませんのでご了承下さい。
記事に関するご感想などございましたら、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「戦略人事が果たすべき役割」
というテーマでお届けします。
先週末、
妻と雑談をしていた時、
妻からこんな話がありました。
「去年の夏にポストが上がって約半年。
これまでずっと前の職場、前の仕事の方が楽しかった。
やりがいもあったと感じてた…」
「正直、いまのポストも、
いまの仕事も全く希望していなかったし、
自分には合ってないと思うし、
私よりもっと相応しい人がいると思ってた…」
「でもね、今日、
創業者の著書を読んでた時、ふと頭に浮かんだの。
以前、福岡支社の時にお世話になった上司の話を…。」
「その上司は、ことあるごとに、
何のためにこの会社で働いてるんだ。
この会社のことが好きか?と言っていた…」
「その言葉を思い出して、気づいたの。
そうだ! 私、この会社が好きで働いてるんだって‥」
「自分の会社が好きなら、どんな仕事でもいいじゃないか…。
そんな風に思えて、いまの仕事にもやりがいを感じられるようになった。」
とまあ、
日本では、よく耳にする
あるあるな話かも知れませんね…。
ここで、
私は気づいたんです。
妻が語る言葉と表情、
そこから感じられる“気”といったものから、
人の思い、愛情、情熱、
そして、言葉の力…
こういったことが、
時間(トキ)やさまざまなプロセスを経て、
人をやる気にさせたり、
覚醒させることがある
ということを。
そして、
「これが人的資本経営の肝かも知れない!」
そう感じました。
具体的に、
どういことかというと…、
経営学という視点から、
経営や人材の問題を考える時、
実は、2つのアプローチがあるんです。
1つは、
事業環境の変化にいかに適応するかを
起点に経営や事業戦略を考え、
その戦略に基づいて人事を行う
「ポジショニング・ベースト・ビュー」
というアプローチ。
そして、
もう1つは、
社内の人財という経営資源を
起点に事業戦略を考える
「リソース・ベースト・ビュー」
というアプローチ。
ちなみに、
かつて日本が高度成長、
右肩上がりの時代だった頃は、
リソース・ベーストが多かったのです。
ところが、
バブルがはじけて経営環境の変化が
激しくなった頃からは、
ポジショニング・ベーストが多くなりました。
そして、
VUCAの時代、
乱世といわれるいまは、
先の2つのアプローチのどちらかということでなく、
2つのアプローチを巧みに駆使しながら
適応していく時代になったのです。
とはいえ、
2つのアプローチを巧みに駆使するのは、
そう簡単ではないというのが現実。
そこで重要な鍵となり得るのが、
“パーパス”
組織戦略の裏側にある
組織の思い、パーパスと、
働く人、個人の思い、
パーパスを繋げてマッチさせる。
これこそが、
人的資本経営の肝だと
私は思います。
人事が、
人的資本経営を推進するにあたって、
ひとつの
管理部門としてでなく、
戦略人事として変容し、
果たしていくべき役割は…、
組織のパーパスと
個人のパーパスを繋いでマッチさせ、
最大化させること。
そのために必要な
ジャーニーを構築すること。
ここにあると
私は思います。
なぜなら、
人的資本経営とは、
人材を「資本」として捉え、
その価値を最大限に引き出すことで、
中長期的な企業価値向上につなげる
経営のあり方とされているから。
ラーニングジャーニー
構築にあたって、
外部のリソースが必要な時は、
お声掛け下さい。
上から目線で
コンサルするのでなく、
内部資源を覚醒させるような
ファシリテートを心がけています。
もちろん、
妻との雑談量を
増やして伺います…。(笑)
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
先週土曜日、
妻の誕生日祝いに
銀座で食事をした後、
日本橋にある、
分身ロボットカフェ
「DAWN」
に行ってきました。
このお店は、
オリィ研究所が
運営しているのですが、
特徴としては…、
身体に障害などをもった
外出困難な方が、
『OriHime』と 『OriHime-D』
というロボットを遠隔操作し、
自宅などから接客してくれる。
そんな新感覚のカフェなのです。
実際に、
事前予約をして、
接客を受けてきました。
時間にすること約30分。
未知の体験や、
テクノロジーに触れて得られた
学びはもちろんのこと。
外出困難な状況にも関わらず、
明るく、楽しく、前向きに、
私たちと接してくれる姿勢を肌で感じて、
色々と考えさせられました…。
今月は、
札幌でキャラバンも
行われるそうです。
ご興味ある方は、
チェックしてみて下さい。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「人的資本経営とは?」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ここしばらく
何かと目にし、耳にする
“Z世代”
その特徴は、
さまざまな場で語られていますが、
今日、この場では、
まったく利害関係のない
10名のZ世代現役ビジネスパーソンを
集めた座談会から見えてきた本音を、
整理してお届けします。
生まれた時からネットがあって、
小学生になれば塾や習い事で毎日とにかく忙しい。
中学生になればSNS経由で、
24時間、世界のニュースにもアクセス可能。
それゆえ、他の世代に比べて国際問題への関心が高く、
道徳意識も高い。
リーマンショックの不況の影響を受けた
X世代を親にもつ世代でもあるため、
金銭感覚は堅実で、実利を求めていく世代でもある。
新しい友だちをつくるのに、
必ずしも対面である必要はなく、
SNS経由もごく普通なこと。
加えて、
一流やオタクと言われる人の情報にも
ネットで日常的に触れているので、
自分自身の現在位置や限界もなんとなく感じている。
1つのことに絞るのが不安で、
多くのことを早く、広く、浅く、
“かじる”世代。
グローバルに活躍する視点をもっている人がいる一方、
実は、内向きで保守的な志向をもっている人が多い…
といった感じです。
さて、
来る4月からの
Z世代の新人研修プログラムは、
お決まりですか?
「実は、これからなんです…」
もし、そういった状況でしたら、
どうぞ、
お気軽にご連絡下さい。
上記のような
Z世代のインサイトを踏まえた
学びの提供が可能です。
研修講師の派遣はもちろんのこと。
内製化支援も対応可能です。
記事に関するご感想などございましたら、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「人を見る目を養うには…」
というテーマでお届けします。
先日、
トヨタ自動車の豊田社長が辞任し、
後任に、エンジニア出身の53歳。
佐藤恒治氏を起用する人事の発表がありました。
日本を代表する企業の
予想だにしないトップ交代の報道に、
思わず、目が釘付けになった方もいるでしょう…。
組織の中で行われる
あらゆる意志決定のうち、
トップや幹部人事ほど
重要なものはありません。
その組織を代表する人として、
人間性、能力、実績、将来性等を見極め、
それに相応しいかどうか判断される訳ですが、
その決断がどれほど困難なものなのかは、
なんとなく想像できるでしょう。
かの経営学者
P.Fドラッカー氏も、
「トップ人事はギャンブルだ」
そう、著書
『ドラッカー 365の金言』
の中で述べています。
現在、
人物評価については、
先人たちからのさまざまな教えが
ありますが、
今日は、
陽明学者であり思想家の
安岡正篤氏の
人物を観る
“八観法゛
という
教えをご紹介したいと思います。
「八観法」
----------------------------------------------------------------------
1、「通ずれば其(そ)の礼する所を観る」
出世した人に対しては、その礼儀正しさを見ると良いでしょう。
いつも謙虚でマナーの良い人もいれば、出世したことで傲慢になり、
礼儀やマナーを無視する人もいます。
礼儀正しいかどうか、ここに人間の品格が現れます。
2、「貴(たか)ければ其の進むる所を観る」
地位の高い人に対しては、その人が使っているものや、
そばにいる人を見ると良いでしょう。
「類は友を呼ぶ」と言われるように、
周りを見ればその人の好みや人格が垣間見えます。
3、「富めば其の養う所を観る」
お金持ちの人に対しては、お金の使い方を見ると良いでしょう。
貧しい時は生活に追われて自分の欲を満たすことにまで手が回りませんが、
お金に余裕ができた時にそのお金を何に使うか、ここに人間の本性が現れます。
お金の使い方を見ると、その人の人生観や倫理観まで分かるのです。
4、「聴けば其の行う所を観る」
人の言動をよく観察しましょう。
発言と行動が一致しているかどうかで、その人が誠実か否か分かります。
5、「習えば其の言う所を観る」
余暇の過ごし方を見ると、その人の人生観の側面が見えてきます。
職場などの公式の場での振る舞いよりも、
休日や余暇の過ごし方にこそ本質的な価値観が現れやすいのです。
6、「止(いた)れば其の好む所を観る」
親しい人と気楽な雰囲気の中で交わした言葉は、
人の本心を反映しやすいものです。
そういう場での発言こそ、注意して観察すべきです。
7、「窮すれば其の受けざる所を観る」
生活に困っていても、受けてはいけない援助や利益があります。
受けるべきではない援助や利益を受けているか否か、
そこにも人の品格が現れます。
8、「賎なれば其の為(な)さざる所を観る」
地位が低く、弱い立場に置かれた人でも、
自分の利益や出世のためにやってはいけないことがあります。
やるべきではないことを控えられるか否かで、
真に志があるかどうかが分かります。
※ 弊社HPには、こういった話の特集ページもございます。
----------------------------------------------------------------------
上記のように、
人物の真価については、
さまざままな場面を観ての判断となります。
「なるほど、そんなものかな…」
そう思われた方もいると思います。
一方、
「トップや幹部人事の
意思決定に携わることはないし…」
そう感じている人もいるでしょう。
とはいえ、
私たちの人生、キャリアは、
どんな人と付き合うかの影響を
少なからず受けるものです。
限られた日々の大切な時間を
どんな人と一緒に過ごすのかは
もちろんのこと。
社内の人事や、
付き合う顧客、業者選定にあたる際などにも
役立つ指針になるはずです。
人を見る目を養い、
それを活かすことは、
役職や地位が、
上がれば上がるほど
重要なものとなります。
そして…、
人物評価する
立場になるということは、
周囲から自分自身が、
人物評価されるということも
忘れてはなりません。
今日の結びは、
自戒の意味も込めて…。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
早いもので、
1月も下旬ですね。
最強寒波の影響は、
受けていませんか?
移動や外出される際には、
時間にバッファを設けて、
安全第一、健康第一で、
乗り切って参りましょう。
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「リスキリングを分かりやすく解説」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「いよいよ、うちの組織でも、
本格的にDXを推進していこう」
そうお考えでしたら、
こういった選択肢もあります。
AI歴25年。
言ってみれば、
AIのスペシャリストと言ってもいい、
遠藤太一郎さんによる、
「AI/データ活用/DX
「何をしよう」がクリアに決まるオンライン講座」
ホームページには、
掲載していない隠し玉です。(笑)
遠藤さんは、
現在、エクサウィザーズの
AIエンジニアリングフェローで、
東京学芸大学 教育AI研究プログラム 准教授、
理化学研究所API 客員研究員という肩書を
もっています。
『次世代AI戦略2025』(日経BP)
の代表著者でもあります。
この講座の特徴は、
半日、1日といった単発の研修でなく、
実際に自分の仕事のネタを使いつつ、
オンデマンドで学ぶこと。
受講修了後、
自走できるようになることを
ゴールにしているところにあります。
決して安価ではありませんが、
実務で使えるDX人材の育成をお考えであれば、
むしろ、費用対効果は高いのではないかと思います。
詳細資料をご希望の方は、
このメールに、団体名、所属、お名前、
日中連絡のつく電話番号、メールアドレスを記載し、
返信して下さい。
記事に関するご感想などございましたら、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「人的資本経営とは?」
というテーマでお届けします。
まず、
「人的資本経営」とは何か?
ということですが…、
人材を「資本」として捉え、
その価値を最大限に引き出すことで、
中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方
(以上、経済産業省HPより抜粋)
ということになります。
また、
その実現に向けた検討会が
経済産業省主導で行われ、
座長・伊藤邦雄氏(一橋大学名誉教授)が
とりまとめたレポート
「人材版伊藤レポート2.0」は、
人的資本経営に向けた課題と解決策を
取りまとめたものとして知られています。
同レポートの中では、
人的資本経営を成功に導くために、
下記、5つの共通項をあげています。
1,動的人材ポートフォリオ
2,知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
3,リスキル・学びなおし
4,社員エンゲージメント
5,時間や場所にとらわれない働き方
詳細は、経済産業省のHPからご確認下さい。
まさに、
仰る通りだなと思う訳ですが、
日ごろ、
官民問わず、
さまざまな組織に伺っている
私の肌感覚からすると…、
この5つを全部やるのは、
リソースフルな組織でない限り、
結構しんどいのでは…
そう感じてしまう部分があります。
もちろん、
5つすべて実行できる
リソース、ポテンシャルがある組織は、
それを目指すのが良いのだと思います。
とはいえ、
あなたの組織が、
そこまでリソースフルでないと
いうことであれば…、
本当に、
先の5つ共通項を
全部やらないと成功しないのか?
ということを、
自社によく当てはめて考え、
出来るところから始めてみましょう。
たとえば、
分かりやすい例として、
仕事が多様化、複雑化して、
なかなか思うように進まない…。
そういった課題が
顕在化しているのであれば、
まずは、
仕事の棚卸しと切り分けをし、
ルーティンワーク部分を、
デジタル活用によって効率化する。
そのために必要な
リテラシーとスキル向上を目的として、
リスキリングする
といった感じでしょうか。
そして、
ここで
私が大事だと思うのは、
何に取り組むかは、
大手のコンサルが
勧めているからやる。
目新しいからやる。
他社がやり始めたから、
うちもやる。
人事のバズワードに
なっているからやる
といったことでなく、
誰の、
何のためにやるのか?
といった
目的を確認して
進めていきましょう
ということです。
従業員を
人的資本と捉えるのであれば、
人を人として扱い、
人として扱われる仕事ができる。
人間味のない
作業や仕事は自動化し、
人が相互信頼のもとに、
ワクワク、成長意欲をもって
仕事に関われる場をつくる。
そう従業員が感じられる
場としての組織を目指すことが、
大切なんじゃないかなと
思います。
あなたの組織の
競争力を高め、
組織価値の向上に繋がるのは、
どんなことでしょうか。
そういった
仕組み構築の過程で、
人材育成が分かる
外部のファシリテーターが必要でしたら、
お声掛け下さい。
目的実現、課題解決に
貢献いたします。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
今週は、
九州佐賀に来ております。
今回の出張も
研修が終わった後は、
オンラインミーティングや
ジムでのスイミングなど精力的に動き、
充実した時間を過ごせました。
今晩は、最終日なので、
少し早めに仕事を切り上げて、
活イカの刺身でもいただきながら、
軽く一杯、地酒を楽しみたいと思います。(笑)
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「ナポレオン流、目標設定術とは?」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2021年12月に行われた
ATDジャパンサミットで
登壇した際、
米国ATD本部の
アジア太平洋マネジャー、
Jacqueline Xu氏より、
「世界最先端のトレーニングスタイル」
そう評価していただいた
五十嵐式自律型人材育成プログラム。
このプログラムの特徴は、
1,時間の使い方をレベルアップして、
仕事のパフォーマンスと生活の質を向上させる
“段取り・タイムマネジメント力”
2,対人関係能力を磨いて、
ご縁や出会い、成長のチャンスを広げる
“コミュニケーション力”
3, 自分の持ち味、価値観を理解して、
自分の活かし方を磨く
“キャリア・オーナーシップ”、“チャレンジ精神“
が同時に身につくことにあります。
少しだけハードな
3か月間の学びの場になりますが、
単発研修ではない学びの場、
自律型人材の育成をとお考えの場合は、
選択肢の1つとして、
ぜひ、ご検討してみて下さい。
以下URLから、
30秒のイメージ動画をご覧いただけます。
記事に関するご感想などございましたら、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「リスキリングを分かりやすく解説」
というテーマでお届けします。
昨年、
総理が所信表明演説の中で話され、
一気に国内でも機運が高まった
“リスキリング”。
すでに、
貴社でも取り組んでおられるかも
知れませんね。
とはいえ、
実際のところは、
まだまだこれから
という組織が多いように
感じております。
そこで、改めて、
「リスキリングとは何か?」
ということについて
触れておきたいと思います。
リスキリングとは、
「組織が変革にもとづいて、
組織が責任をもって従業員を再教育すること。」
現在は、
DX(デジタルトランスフォーメーション)が
大きなテーマになっています。
これを
従業員目線で考えると…、
「新しいことを学び、新しいスキルを身につけ、
それを実践し、新しい職業・仕事につくこと」
となります。
リスキリングと
類似する言葉に、
リカレント教育というものがありますが、
似て非なるものになります。
ちなみに、
リカレント教育と
リスキリングの違いは、
リカレント教育が、
個人の興味・関心で学び、
必ずしも仕事に直結しなくても
良いものであると同時に、
新しいことを学ぶにあたって
職を離れることが前提になっている
のに対して、
リスキリングは、
いま従業員がもっているスキルと
これから必要になるスキル(フューチャースキル)の
ギャップ(スキルギャップ)を埋めることを組織目的とし、
学習 → スキル習得 → 職業転換
までを目指すもの
という点で相違しています。
したがって、
リスキリングに取り組む大前提は、
現時点での従業員のスキルの
可視化にあります。
これを欧米、シンガポールでは、
スキルズ・タクソノミーといっていますが、
まずは、
ここがスタートラインだと
いうことを押さえておきましょう。
また、
組織がリスキリングを
実行する前段階でよくある話として、
トップや経営幹部が、
「従業員に学び直しなんかさせたら、
転職してしまうじゃないか…」
そんなことを懸念して、
リスキリングの導入に、
二の足を踏んでしまう…
そんな光景を
目にしたり、耳にしたり
することがあります。
事実、
組織がリスキリングに取り組めば、
転職する従業員は出てくるでしょう。
一方、
「この会社にいたら、
自分は成長できる」
そう思って、
転職予備軍だった人が
とどまることもあるでしょうし、
他社や他の団体から、
欲しい人材が、
転職してくることもあるでしょう。
従って、
大切なことは…、
自社の人材を囲い込もうとすることでなく、
退社しても、また戻ってこれる雰囲気、
社風をつくることにあります。
先のサッカーW杯において、
国内の観戦をネットで放送した
某ネット系の企業では、
社内の優秀な人材、
エース級の人材を、
どんどん新規事業の部署に
意図的に移動させて、
なんとなく、
社内に会社の方向性を
感じさせる。
そして、
その部署に、
自分も行った方がいいんだな…、
そう社員に思わせて、
そのための努力、
自己啓発を促すといった
仕組みを作っているようです。
これも、
上手いやり方の1つですよね。
たとえるなら、
『馬を水飲み場に連れていくことはできても、
水を飲ませることはできない。』
といったイメージでしょうか。(笑)
また、
これは、
ある転職エージェントから
聞いた話ですが、
一般的に、
人が転職を考えるのは、
1,やりがい、2,働く仲間、3,給与
この3つのうち2つのバランスが
崩れると辞めてしまうとそうです。
ですから、
逆にいうと、
この3つの
ポイントを押さえれば良い
ということなのかも知れません。
日本企業も、
終身雇用の時代は終わった…
そんな話を
耳にする時代だからこそ、
従業員が
自発的に学びたくなる、
ラーニングカルチャーを
いかに社内に醸成していけるかが、
重要な経営課題と言えます。
お役に立てることがあれば、
いつでもご相談ください。
では!
こんにちは。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
前回の配信、
「年始に20の教訓…」
に対して、
お返事などいただいた皆さま、
ありがとうございます。
「新年早々、良い刺激になった」
といった内容の数々を拝見し、
私のモチベーションも
さらに、上がりました!(笑)
それでは、
今週も、
前向きなエネルギーを
届けて参ります!
元気出していきましょう!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
■ 明るく、楽しく、前向きに!なるヒント ■
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
今号も、
あなたの仕事が
笑顔と感謝あふれるものとなるよう、
思いを込めてお届けします。
さて、前回のメルマガでは、
「年始に20の教訓…」
というテーマでお届けしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この1年間、
円相場は、大きく変動し、
私たちの日常生活に、
さまざまな影響を与えて参りました。
それと同時に、
将来へのお金の不安は、
さらに増したように感じます…。
弊社では、
従業員の皆さまの、
そんな不安解消の一助として、
お役立ていただきたく、
従業員のマネー教育、
マネープランを絡めたキャリアデザイン研修を、
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
の講師によって提供しております。
IFAの存在は、
この1年の間で、
だいぶ浸透してきたように思います。
欧米では弁護士、医者とともに、
個人に必要な専門家として広く認知されている
IFAの講師が提供するプログラムによって、
従業員のマネーリテラシーを高めつつ、
将来設計、キャリアを考えていただくことは、
個人にとっても、組織にとってもメリットがあります。
具体的に、
ご検討いただける場合は、
お気軽にご連絡下さい。
記事に関するご感想などございましたら、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、
「ナポレオン流、目標設定術とは?」
というテーマでお届けします。
質問ですが、
あなたは、
年始に目標を立てる派ですか?
それとも、
立てない派ですか?
かの有名な
フランスの皇帝
ナポレオンは、
「計画どおりに事が運んで
戦いに勝つなんてあり得ない」
そう言っていたそうです。
「な~んだ、
それなら目標や計画なんて、
立てても意味ないじゃないか」
そう思われるかも知れませんが、
実は…、
そのナポレオン、
戦いの前には、
しっかり目標を立て、
これでもか、
これでもかという位、
綿密に、綿密に、
計画を立てていたそうです。
それは、
一体、なぜか?
答えは…、
目標や計画なしで行動すると、
目の前のこと、今やっていることに、
どうしても意識が引っ張られてしまう。
結果、
いまやっていることに、
どんな意味があるのか?
そもそも、
本当に重要なことは何なのか?
といったことが、
分からなくなってしまうからだそうです。
私たちの日常は、
日々、やることに溢れています。
「年始早々、
なんでこんなに忙しいんだろう…。」
そう思っている人も
少なくないはずです。
来る日も、来る日も、
目の前にやることがたくさんあって、
ついつい、
今年一年、
自分にとって大事なことは何か?
今年一年、
自分が大切にしたいことは何か?
といった
本当は重要なことを、
すっかり、
どこかに忘れてしまい、
どうでも良いようなことに
振り回されてしまう…
そんなことが起きがちです。
インド人の経営学者
スマントラ・ゴシャール氏は、
このような状態を、
“アクティブ・ノンアクション”
と表現しています。
立てた目標や計画が、
予定通りに進むことは、
安心感が得らえて嬉しいものです。
しかし、
それと同等、それ以上に
私が重要だと思うのは、
立てた目標や計画が、
その一年、
自分の拠りどころとなって、
大切なことに
引き戻してくれる。
そこに
あるのではないかと。
ということで、
今日のまとめです。
「目標や計画は、
立てないより、立てた方が良い。」
そして、
目標や計画を立てることで
得られるものは、
達成に向けた
プロセスの中で、
「本当に重要なことに
フォーカスできるようになる」
ということにあります。
最後に、
おまけでもう1つ…、
新年を迎えると、
なぜか人は、
新しいことを始めたいという
思いが強くなるようです。
昨年立てた目標は、
達成されていなくても
今年に引き継がれることなく、
また1から、
新しい目標を設定することが
あるようです。
それは、
それでありだと思いますが、
必ずしも、
毎年、毎年、
新しい目標を
立てなくても良い。
昨年立てた目標が
達成されていなければ、
引き継いで、
今年の目標としても良い
ということも
押さえておきたいところです。
2023年も、
あなたにとって、
私にとって、
充実した1年となりますよう…
では!
新年おめでとうございます。
人づくりアーティストの
五十嵐です。
3年ぶりに
行動制限のない年末年始。
いかがお過ごしでしたか?
私は、
年末は伊豆の温泉に足を運んで、
1年の疲れを癒し、
年始は、
東京と福岡の実家に
挨拶まわりを済ませ、
あっという間に
終わってしまいました…。
せっかく癒した疲れが戻ったような
気がしない訳でもありませんが…、(笑)
十分リフレッシュ出来たので、
今年も張り切ってスタートしてます!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
人前で話す機会が増えたら読んで欲しい、
講師の基本書。
(あさ出版・1,650円)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
さて、本題です。
年始の配信は、
「目標設定の前にしておくこと…」
というテーマでお届けします。
質問ですが、
この年始に、
今年の目標は設定されましたか?
「はい、バッチリです!」
という方は、
素晴らしいと思います。
一方、
「実は、この3連休で…」
という方や、
「どうしようか考え中です…」
という方は、
ぜひ、
今日の話を参考に
してみて下さいね。
新年を迎えると、
人は、
なぜか新しいことを始めたいという
思いが強くなるようです。
昨年立てた目標は、
達成されていなくても
今年に引き継がれることなく、
また1から、
新しい目標を設定したり
することが多いようです。
新年を迎えるたびに、
毎年、毎年、
新しい目標を立てては、
達成されずに終わる…
そんな経験、
一度や二度ありませんか?
実は、これ、
あることが原因で
起こることなんです。
その
「あること」とは…、
たとえば、
ダイエットを例にすると、
「今年は、ダイエットを頑張る!」
といった
単なる決意表明を
目標と錯覚していたり、
「来週から、週2回、
オンラインでヨガレッスンを受けて、
12月31日までに100時間トレーニングする。」
といった、
行動目標やタスク管理レベルで
とどまっていたり
することにあるんです。
一見、
良さそうに思える
先の行動目標ですが、
何がダメなのかというと、
それは、
やっているうちに、
知らず知らず、
こなすことが目標に変わって
いってしまうからなんです。
「いま11月第1週で70時間。
達成するには、これから毎週10時間やらなきゃ…」
といった感じでしょうか。
では、
一体、どうすれば良いのか?
ということですが、
一言でいえば…、
「目標は、
ワクワクするように設定する」
というのが
ポイントです。
たとえば、
先のダイエットなら、
ヨガレッスンでダイエット出来たら、
どんな良いことが待っているのか?
「モデルの●●さんが着ている
あのスーツが似合う自分」
「柔軟な体を手に入れて、
美しいフォームで皇居の周りを
ランニングしている自分の姿」
「引き締まった
自分の体型に自信が持てて、
人前で堂々と話している私」
といった感じです。
という訳で、
今日のまとめです。
目標設定は、
意気込み、決意表明でなく、
数値化さえすれば
良いというものでもなく、
その目標が達成された時、
自分にとって、
どんな素敵なイメージが待っていて、
そのイメージが実現した時、
ワクワクするのかどうか
といったことが重要
ということでした。
私も、
今年の目標を
設定しました。
1つは、
今年、1年間の目標。
もう1つは、
今年から数年かけて
取り組む目標。
具体的な中身は、
ナイショです!(笑)
でも、
いずれそのうち、
このメルマガなどでも、
触れていくことになるかと思います。
今年も良い一年にしていきましょう!
では!
サイドメニュー
- ★選ばれる理由●
- 講師紹介
- 事例一覧2
- 川口鋳物工業協同組合様
- 愛媛県研修所
- 佐賀県自治研修所
- 蕨市役所
- IAC様
- 静岡県湖西市役所
- 佐倉市役所
- 千葉市
- 大分県自治人材育成センター
- 事例一覧3
- 下田市役所
- 宮崎県市町村職員研修センター
- 鹿児島県
- 江戸川区
- 足利市
- 宮崎県市町村
- 伊勢崎市
- ニュース一覧
- 調達企業一覧(補足資料)
- 監修者
- 資料請求ありがとうございました
- 求人情報
- ピックアップ!
- 人材育成に関するコラム
- お客様の声(2022年度)
- お客様の声(2021年度)
- お客様の声(2020年度)
- 書籍購入
- 特典動画のお申し込み確認
- ダイレクトメール
- メディア掲載・その他
- 個人情報保護方針
- 無料個別相談会(オンライン)
- 無料個別相談会のお申し込み確認
- メールマガジン登録
- メルマガ登録ありがとうございました
- メルマガ登録を解除いたしました
- 研修一覧