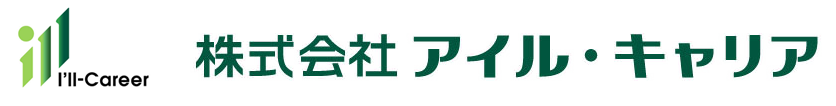社内コミュニケーションを活性化させる9つの施策を解説!
他社の成功事例も紹介
働き方が多様化し、改めて社内コミュニケーションの重要性が注目されています。社内コミュニケーションの減少は、生産性の低下や離職率上昇を招く要因になり得ます。そこで、本記事では、社内コミュニケーションを活性化させる9つの施策について解説します。他社での成功事例も紹介いたしますので、社内コミュニケーションの活性化にご興味あれば、ぜひ参考にしてください。
社内コミュニケーションとは

一般的に、社内コミュニケーションとは、社員間で行われる情報共有や情報交換を指します。業務に関する内容だけでなく、雑談やランチ、社内イベント、サークルなども社内コミュニケーションの一つです。近年、働き方、価値観の多様化によって、社内コミュニケーションが機能不全になっている会社が増加しているようです。
社内コミュニケーションが必要とされる理由
社内コミュニケーションは、社員同士が良好な人間関係を構築し、働きやすい環境を作るために重要です。エン・ジャパン株式会社の調査によれば「本当の退職理由」として約4割の人が「職場の人間関係の悪さが退職理由である」と答えています。
参考:「本当の退職理由」実態調査
社内のコミュニケーション不足は、働きやすい環境にマイナスの影響を与えるだけでなく、離職率の増加にも繋がります。社内の人間関係や職場環境を良好に保つためにも、社内コミュニケーションの活性化が必要と言えます。
社内コミュニケーションを活性化させる4つのメリット

社内コミュニケーションの活性化は、風通しの良い雰囲気、職場作りを支え、生産性の向上や顧客満足度向上にもプラスに寄与します。そこで、会社が社内コミュニケーションの活性化にコミットメントすることで得られるメリットについて、具体的に解説します。
1、社員の仕事に対するモチベーションが増加する
社内コミュニケーションが活発な会社は、心理的安全性も高まり、社員が自由に、積極的に意見やアイディアを言える雰囲気が醸成されます。そういった社内の雰囲気、組織風洞が社員の自発性を引き出し、モチベーションやエンゲージメントの向上を促します。
2、社員の定着率が上がる
良好な社内コミュニケーションは、職場の良好な人間関係をもたらし、社員の離職を抑止し、定着率の向上にも繋がります。たとえば、上司と部下のコミュニケーションが増えることによって、上司は部下の不満や悩みに早い段階で気づくことが可能となり、タイムリーにフォローや支援といった手が打てるようになるといったことがあります。
3、会社の生産性が高まる
心理的安全性のもとにコミュニケーションが取れる職場環境を構築できれば、社員同士の情報共有や交換も増え、結果、新たなアイディアを生み出すことや業務改善なども自然と行われる風土が育めます。また、部署内はもちろんのこと、部署を超えた連携や協力へと繫がり、組織力、生産性が向上します。トラブル発生時などには、日ごろのコミュニケーションがものを言い、部門を超えた情報共有や連携をもとに生まれる効果的な対応が可能となり、トラブルの早期解決にも繋がり得ます。
4、顧客満足度が向上する
部署を超えた情報交換や連携をもとになされる顧客への対応は、顧客対応の質やレベルも向上させ、顧客満足度の向上にも繋がります。また、顧客ニーズを満たす商品やサービスの開発も可能となり、新たなヒット商品やイノベーションを生み出し、事業拡大にも貢献し得ます。
関連記事
■Z世代の特徴や欠点に合わせた効果的な育成方法とは?NGな叱り方も紹介
■株式会社アイル・キャリアが提供するコミュニケーション研修
社内コミュニケーションを活性化させる9つの施策

これまでみてきたように、社内コミュニケーションの活性化は、社員のモチベーションや生産性向上に重要な要素です。以下で紹介する施策を実践し、社内コミュニケーションの活性化を図りましょう。
1、全社的な社内イベント
賛否両論はあるものの、全社イベントは、部門を超えた情報共有や交換を活発化させるために効果的です。定期、不定期、各社の事情に合わせて社内イベントを開催し、会社全体で社員同士の交流を促すことは、単に、社内コミュニケーションの活性化にとどまるだけでなく、一体感の醸成にもプラスとなり得ます。具体的なイベントの例としては、社員運動会や部署対抗のクイズ大会などが挙げられます。
2、フリーアドレス制
仕事の内容も考慮した上で設計されたフリーアドレス制の導入は、社内コミュニケーションの活性化に一役買います。社員が固定化された席でなく、自由な席で働くことによって、社員間の偶発的なコミュニケーションを意図的に生み出すことが可能となり、そこから生まれるアイディアなどがさまざまな効果を生み出すことがあります。ただし、定型的な業務をチームで行う必要がある管理部門などに導入しようとする場合は、メリット、デメリットも整理した上で、慎重に導入の可否を判断することが求められます。
3、社員食堂や社内カフェ
社員食堂や社内カフェは、社員間のカジュアルなコミュニケーションを促進する場となります。食事やお茶を飲みながら職場より気軽に話せる雰囲気は、オープンなコミュニケーションに必要な要素です。私生活の話や趣味の話など、お互いの人となりを理解することに繋がり、豊かな関係性を育みます。それなりにコストのかかる取組みとなりますが、費用対効果も踏まえ、検討してみましょう。
4、社内SNSやブログを活用した情報発信
社内SNSやブログは、社内報よりもより気軽に情報を発信できるうえ、コストも抑えられます。イベントの日程やサークル・部活動の内容・部署ごとの情報などを発信すれば、普段は関わる機会がない部署の仕事内容や社員を知るきっかけにもなるので、効果的に活用しましょう。
5、ミーティングルームの設置
ミーティングルームは会議に使用するだけでなく、相談しにくい内容を相談できる場としての活用も可能です。オープンなミーティングスペースなら、社員が休憩スペースとしても利用できるのでおすすめです。社内に休憩スペースがあることで、社員がスキマ時間でリフレッシュすることが可能となり、そういった安心感のようなものがストレス対策にも相応の効果をもたらします。
6、社内コミュニケーション活性化ツール
社内コミュニケーション活性化ツールを活用すると、対面だとためらってしまう相談ごとや悩み、質問が気軽にできます。また、部門や部署を超えた情報共有や情報交換も容易となるため積極的に導入しましょう。
7、1on1ミーティング
効果的な1on1ミーティングの実施は、上司と部下のコミュニケーションを活性化し、関係構築にプラスに働きます。上司が定期的に部下の話に耳を傾ける場があることで、部下の悩みの早期発見に繋がったり、上司の考えが部下に浸透しやすくなる効果も見込めるでしょう。上司と部下の間で行われる1on1ミーティングなど、効果的に実施しましょう。
8、社内部活やサークルを作る
社内部活やサークルは、社内コミュニケーション活性化におすすめの制度です。共通の趣味を持った人々が集まるため、コミュニケーションのハードルが下がります。また、体を動かすことで、心身の健康にも効果的です。社内部活やサークルを作り、社内コミュニケーションの活性化とともに、社員の心身の健康状態の改善を図りましょう。
9、全社員出社日を決定する
リモート勤務が多い会社では、全社員出社日の決定が効果的な施策の一つとなることがあります。近年では「ハイブリッド勤務」と呼ばれる、リモートワークとオフィス出社を適度に組み合わせた混合型の働き方が注目されています。リモートワークでは難しい表情やしぐさ、声色などの非言語コミュニケーションを取り合うためにも、職種や仕事内容を踏まえ、始めるのも良いでしょう。ただし、社員への説明も不十分なまま強制的に推進するとかえって逆効果となる場合がありますので、実施する目的を忘れず推進しましょう。
社内のコミュニケーションが活性化しない3つの原因

社内コミュニケーションの活性化を図るためには、現状の正確な把握と課題を見える化することが必要です。参考までに、社内コミュニケーションが活性化しない3つの原因を紹介しますので、自社の現状と照らし合わせて読み進めてみましょう。
1、働き方や価値観の多様化
昨今の働き方や価値観の多様化が社内コミュニケーションの活性化の妨げの原因の1つと考えられます。たとえば、人と関わる機会が少ないリモート勤務を望んだり、直接顔を合わせることを避けてチャットやメールで日々のコミュニケーションを取るなどです。タスク系の仕事は業務効率が向上するメリットも多々ありますが、チームや特定の人と協働して進める仕事の場合などは、リモート勤務がベースであっても、定期的に顔出しのオンラインミーティングを実施する。あるいは、定期的に出社して顔を合わせるなどコミュニケーション不足の解消を図ることが必要です。
2、過度な競争や上位下達の社風
部署や個人間の過度な競争は、双方に強いライバル意識を植えつけたり、個人主義に拍車をかける恐れがあります。それにより、本来必要な情報共有や情報交換すらなされず、社内コミュニケーションの大きな妨げとなってしまう場合があります。また、上司が部下を叱責する機会が多かったり、トップダウンの傾向が強ければ強いほど、社員が自由に意見を出しづらく感じてしまうでしょう。
3、縦割りの組織形態
縦割りの組織形態にも良さはありますが、社内コミュニケーションの観点から考えると、社内の交流が閉鎖的になる傾向が強く、コミュニケーションは活性化しません。イベントや社内SNSなどもない場合は、他の部署との関わりが殆どなく、他の部署の社員を知る機会も少なくなります。また、部門・部署・拠点間の関係性が薄いと、情報共有や情報交換の不足に拍車をかける傾向が強くなります。
社内コミュニケーションの活性化を成功させた企業事例5選

社内コミュニケーションの活性化を成功させるためには、自社の課題に最適な施策を行う必要があります。ここでは、コミュニケーションの活性化を成功させた事例を5つご紹介しますので、参考にできる事例がないか見ていきましょう。
1、TSUTAYA STORES:店舗間会議
TSUTAYA STORESでは、経営陣など本部スタッフや店舗統括スタッフ、店舗スタッフがオンラインでコミュニケーションをとれる「店舗間会議」を導入しています。それまで店舗スタッフと会議をする時間や場がなく、コミュニケーション不足と教育不足が課題でした。店舗間会議を取り入れた結果、社内全体でコミュニケーションを気軽にとれるようになり、今までなかった横の繋がりや連携が生まれました。
2、株式会社ウィルゲート:オンラインランチ会
リモートワークを導入していると、新入社員と先輩社員が雑談など気軽なコミュニケーションをとり、信頼関係を深めていくことが困難な場合が多いものです。同社では、入社1ヶ月以内の社員を対象に今後業務で深く関わる先輩と一緒にコミュニケーションがとれるオンラインランチ会を実施しています。オンラインランチ会によって、上下関係を過度に意識することなく気軽に話せる環境の構築に成功しました。
3、株式会社ぐるなび:ウォーキング・ミーティング
同社では、若手社員や社長と話したい社員を対象にウォーキングを兼ねた会議を定期的に開催しています。会議室といった閉ざされた空間ではなくオープンな空間で会話することで、社員が気軽にコミュニケーションをとれるようになりました。また、歩くことで頭が冴え、新たなアイディアを生み出すうえでも効果的です。
4、トレンダーズ株式会社:おごり自販機
同社では、社員証を2人でタッチすると飲み物が無料でもらえる「おごり自販機」を導入しています。働き方の変化で、社員同士のコミュニケーションが減っていたのが課題でした。「おごり自販機」の導入後は対面だけでなく、チャットで誘う社員も出てきて、部門や部署を超えた交流も増加しています。
5、テクロ株式会社:1on1ミーティング
同社では、上司と部下が1対1で話し合う1on1ミーティングを導入しています。それまで、フルリモート会議が多く、コミュニケーション不足が課題とされていました。1on1ミーティングを導入することで、業務に関する内容だけでなくプライベートな雑談も気軽にできるようになりコミュニケーションの活性化に成功しています。
関連記事
■Z世代の特徴や欠点に合わせた効果的な育成方法とは?NGな叱り方も紹介
■株式会社アイル・キャリアが提供するコミュニケーション研修
まとめ
今回は、社内コミュニケーションを活性化させる施策や成功事例を紹介しました。離職率が上がる、生産性が下がるなどの課題を解決するためには、コミュニケーションの活性化が最適です。ただし、自社の課題に合った施策でないと良い効果は得られません。自社の現状を把握し課題を分析したうえで、適切な施策を行い社内のコミュニケーションを活性化させましょう。
<<前の記事 次の記事>>リスキリングとリカレントの違いとは? Z世代の特徴や欠点に合わせた効果的な育成方法とは?
導入するメリット・デメリットを解説
この記事の監修者
株式会社アイルキャリアは、お客様ごとに抱える課題や目標に合わせたオーダーメイドプログラムで”学び”を提供する研修会社です。官公庁・自治体から上場企業、医療法人や学校法人まで様々なお客様に対して、ご要望と時流をふまえた必要な”学び”を、新人から管理職まで幅広く提供し、組織の人材育成を支援しております。特徴としては、その研修で達成したい目標(行動変容)の先にある成果、パフォーマンス(行動変容の結果得らえるもの)までを意識してプログラムを作成することにあります。
サイドメニュー
- ★選ばれる理由●
- 講師紹介
- 事例一覧2
- 川口鋳物工業協同組合様
- 愛媛県研修所
- 佐賀県自治研修所
- 蕨市役所
- IAC様
- 静岡県湖西市役所
- 佐倉市役所
- 千葉市
- 大分県自治人材育成センター
- 事例一覧3
- 下田市役所
- 宮崎県市町村職員研修センター
- 鹿児島県
- 江戸川区
- 足利市
- 宮崎県市町村
- 伊勢崎市
- 労働生産性の向上-1
- タイムマネジメントが上手い人の特徴とスキル:仕事の生産性を高める秘訣とは?
- 【タイムマネジメント研修とは】 実施する理由や効果まで包括的に解説いたします
- タイムマネジメント方法の完全ガイド
- タイムマネジメント能力を高めるための実践ガイド
- 効果的なタイムマネジメント研修の選び方
- 「仕事の見える化」は業務の効率化に必須 【タスクを可視化する研修を紹介】
- 仕事の優先順位づけとは? 業務を効率化するためポイント・研修を紹介
- イレギュラー対応力を分析して生産性を上げる 【すぐ使えるスキルから研修まで】
- チームパフォーマンス向上研修で変わる職場 【組織としての成長を目指して】
- 労働生産性の向上-2
- 正しい育成方法で新人・若手社員の早期育成を実現する 【研修で意識すること】
- 仕事の効率化に結びつく具体的な方法を提案 【即効性のある研修も紹介】
- 自律型人材とは?求められる背景やメリット・デメリット、育成方法を解説
- オンボーディングは早期離職を解決するカギ!実施時のポイントや事例も紹介
- 【新人の早期育成】 即戦力を育てるために取り組むべきことを解説します
- 時間管理の効果的な方法とツールの徹底解説
- 生産性を向上させるための秘訣とは 【組織レベルから個人まで対応】
- 時間の使い方が上手になる方法は? 成果が上がる時間管理術を紹介
- プレイングマネジャーの仕事術とは?役割や効率化のコツを解説
- 労働生産性の向上-3
- プレイングマネジャーの悩みを解決する時間管理術とは?
- タレントマネジメントとは?導入手順やメリット・デメリットも紹介
- テレワーク・在宅勤務導入後の労働時間管理におすすめの方法 3選
- スピード仕事術を身に付けよう!仕事を効率化させるテクニック
- タスク管理を上達させて仕事を効率化させよう! 役立つツールの紹介も
- 企業におけるエンゲージメントの意味とは? 向上させる方法もあわせて解説
- ハラスメントとは? 会社で重視すべき7つのハラスメントと防止策を解説
- リスキリングとリカレントの違いとは? 導入するメリット・デメリットを解説
- 社内コミュニケーションを活性化させる9つの施策を解説!他社の成功事例も紹介
- 労働生産性の向上-4
- Z世代の特徴や欠点に合わせた効果的な育成方法とは?NGな叱り方も紹介
- VUCAとは?今の時代に適した人材を育成する方法をわかりやすく解説
- 厚生労働省も推進するキャリア自律とは?定義やデメリット・メリットを紹介
- 人事担当者必見!戦略人事の成功事例8選&成果を出す実行ステップ
- 人的資本経営とは?企業・自治体が押さえるべき背景と人材育成の成功ポイント
- 残業削減のための研修や方法を解説!働き方改革で求められる施策
- Z世代も納得!「タイパを極める」ビジネススキル習得術
- ワークスタイル分析で生産性を高める 【すぐに使えるスキルから研修まで】
- 複製用
- 働き方-1
- キャリアデザインとは? 意味や必要性、具体的な支援方法を徹底解説!
- キャリアデザインシートの作成方法と活用の秘訣
- キャリアデザイン研修の効果と実践例
- キャリアデザインの重要性とその実践方法
- 【キャリアの定義とは?】 従業員のキャリア開発が必要な理由を解説
- キャリアの棚卸しの方法とステップガイド
- キャリアチェンジを成功させるための具体的な方法
- どんなキャリアを積みたいかわからない人への、 キャリアプラン作りの基礎解説
- キャリア戦略の重要性 | 人生設計や転職時に役立つワークシートを紹介
- 働き方-2
- キャリアデザインシートの書き方例 | 構成の方法やコツを解説
- キャリアゴールとは何か? ゴール設定の必要性や具体的な設定手法、事例を紹介
- ビジョン達成に必要な考え方やビジョン策定に必要な手順、 企業事例を解説
- キャリアプランニングとは何か? メリットや重要性、実施方法まで詳しく解説
- ビジネスにおいて目標設定が必要な理由とは? 目標設定の具体例やフレームワーク、職種別の例文を解説
- キャリアアセスメントとは? メリット・デメリットや活用できるツールを紹介
- 「生きがいを支える5つの大切なこと」
- 人生の満足度を高める方法
- 今注目の「働き方改革」とは?具体的な取り組みと課題
- 働き方-3
- ワークライフバランスの見直しや実施が 企業と社員にとって必要な理由
- 仕事と家庭の両立法 | 無理なくこなすためのコツ
- 研修理論-1
- 「研修は、人の能力を拡張する」が鍵に… ~「あなたに頼んでよかった」を生み出す、人の領域~
- 2026年 人材育成のトレンド
- 人材育成は、「人が決める場」をつくる仕事だ!
- 「High Impact Learningモデル」
- 「ラーニングピラミッド」
- テクノロジーと人間力を融合した学びの未来
- 「カークパトリックモデルの4段階評価」
- 「パーソナライズされた学習は、誤った仮説に基いている」
- 「知識の保持や適用には望ましい困難が必要」
- 研修理論-2
- 「学習の5段階」
- 「研修のゴールは行動変容ではない!?」
- オンライン研修とは?メリット・デメリット、始め方について徹底解説
- 「サクセス・ケース・メソッド」
- 「プランド・ハプンスタンス・セオリ(ハプンスタンス・ラーニング・セオリ―)」
- 「エキスパート(専門家)になるには」
- ニュース一覧
- 調達企業一覧(補足資料)
- 監修者
- 資料請求ありがとうございました
- 求人情報
- ピックアップ!
- 人材育成に関するコラム
- お客様の声(2022年度)
- お客様の声(2021年度)
- お客様の声(2020年度)
- 書籍購入
- 特典動画のお申し込み確認
- ダイレクトメール
- メディア掲載・その他
- 個人情報保護方針
- 無料個別相談会(オンライン)
- 無料個別相談会のお申し込み確認
- メールマガジン登録
- メルマガ登録ありがとうございました
- メルマガ登録を解除いたしました
- 研修一覧