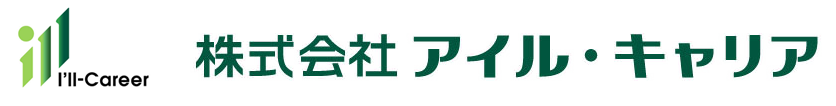「仕事の見える化」は業務の効率化に必須
【タスクを可視化する研修を紹介】
近年、業務の効率化を考える上で「仕事の見える化」が重要視されています。
「仕事の見える化」は、各従業員が抱えているタスクを浮き彫りにし、適切な業務の割り振りができるようになります。
今回は「仕事の見える化」を推進するにあたり、必要なポイントやメリットを解説しつつ、「仕事の見える化」を実現するための研修をご紹介します。
「仕事の見える化」とは?
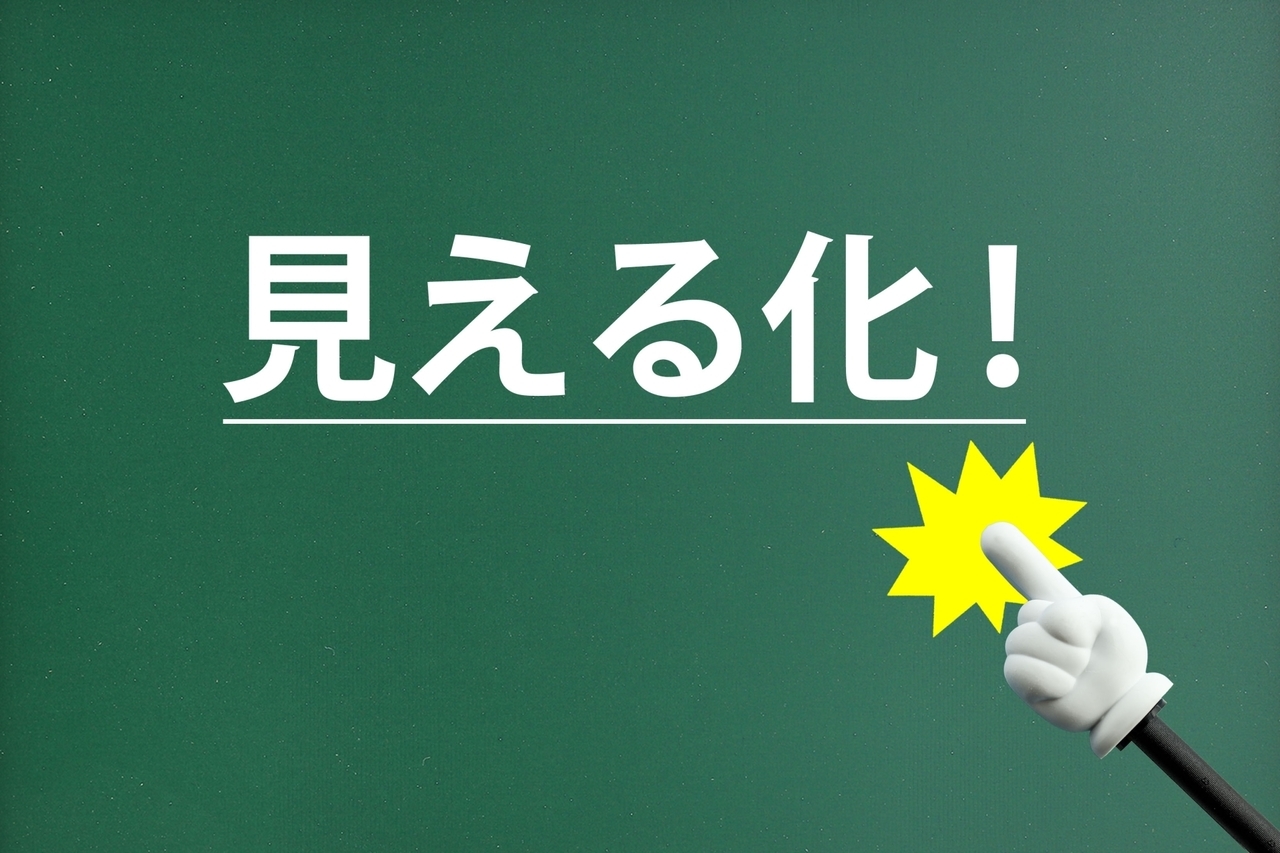
ここでいう仕事の見える化とは、各従業員が「いつ」「どこで」「どのような業務」をしているか把握できる状態をいいます。
近年の人手不足・少子高齢化などにより、さまざまな組織で働き方の見直し、タスクの合理化が求められている中、注目度が向上しています。
仕事の見える化に必要なこと

仕事の見える化に必要なことは、以下の通りです。
- タスク状況の把握
- 業務フローの把握
- ナレッジの共有
- タイムスケジュールの管理
「仕事の見える化」を実施する上で、何から手をつけるべきか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
まずは、どこから手をつけるべきかを順に説明していきます。
タスク状況の把握
まずは、各従業員が抱えているタスクを可視化し、チーム全体の業務量をおおまかに把握します。それによって、無駄な業務を洗い出すことも可能となります。その際、トップダウンで無駄な業務を決めるのではなく、現場と対話をした上で本当に必要なタスクかどうかを判断するようにしましょう。過度な業務を抱えている従業員を把握できれば、業務の割り振りを見直すことも可能となり、退職などのリスクも抑えられるでしょう。
業務フローの把握
業務フローには、個人のフローと組織のフローが存在します。たとえば、営業担当者個人のフローの場合「営業活動→アポイント獲得→商談→契約」といった流れが挙げられます。
業務フローを可視化することで、無駄やムラがないかどうかといった現状の課題や改善ポイントも明確になるでしょう。とはいえ、闇雲に業務フローをコンパクトにしたり、良かれと思って手間暇、負担のかかるフローを追加したりして関係者との情報共有が疎かになってしまうと、ミスが発生しやすくなるので慎重に進めましょう。いずれにしても、商品やサービスの質を向上させながら業務の効率化を行うには、業務フローの把握が入口となります。
ナレッジの共有
ナレッジとは「経験」や「知識」を指す和製英語です。従業員各自が保有するナレッジを可視化し、共有しないと、組織の中に「暗黙知」が増えてしまい、業務の属人化に拍車がかかります。最悪、従業員が退職や休職した際に業務が滞ってしまうようなことも考えらえます。
「暗黙知」を「形式知」へと昇華させる仕組みをつくること、そのために、まずは、業務を見える化することが重要です。
タイムスケジュールの管理
一般的に、タイムスケジュールとは、各従業員が「いつ」「誰と」「どのような業務を」「どこで」行うかの情報をいいます。各従業員のタイムスケジュールをグループウェアなどを活用しながら組織内で共有することは、業務効率化に役立ちます。なぜなら、各従業員のタイムスケジュールによって業務の割り振りなども最適な状態へと修正する必要が出てくるからです。
チームの仕事を円滑に遂行させるためにはタイムスケジュールを見える化し、管理することが必要です。
仕事の見える化がもたらすメリット

仕事の見える化がもたらすメリットには、以下のようなものがあります。
- 生産性の向上
- 問題の早期発見
- 客観的な人事評価
- タスクの平準化
それでは、それぞれ詳しく解説していきましょう。
生産性の向上
「仕事の見える化」により、無駄なタスクやプロセスが可視化されます。無駄を削減した分のリソースを別の業務に割り振ることで、生産性の向上に繋げることが可能です。各従業員の得意分野と苦手分野を正確に把握することと合わせることで、適材適所な人員配置、業務の割り振りも可能となります。
問題の早期発見
管理監督者やプレイングマネジャーが現場の状況を把握できるようになることで、問題の早期発見へと繋げることも可能となります。部下の仕事を単純に見える化するだけではなく、業務上の報連相ルールも標準化することで、業務効率化と問題の早期発見に繋がる仕組みづくりも可能となるでしょう。
客観的な人事評価
客観的な人事評価基準が組織内で共有、浸透されていない組織では、どうしても直属の上長の主観による評価となりがちです。公平性が感じられない人事評価は、従業員のモチベーション低下に繋がり、最悪、離職に繋がることもあります。仕事の見える化とそれをもとにした客観的事実、生み出した成果を勘案し、評価することで、透明性も公平性も保たれた評価制度となっていきます。
タスクの平準化
タスクの平準化とは、従業員ひとり一人のタスクのボリュームを均等にすることをいいます。仕事の見える化は、その前提として必要なものです。平準化によって、一部の従業員へのタスクの偏りを解消し、不平や不満、業務の属人化予防にも繋げることが可能です。公平感ある業務の割り振り、タスクの平準化は、公平な評価にも繋がるという効果も予想されます。
仕事の見える化の手段

「仕事の見える化」にはさまざまな手段があります。今回は、職場ですぐに実行できる方法から、IT技術を活用した手段までご紹介します。
業務内容のヒアリングと報告プロセスの策定
所属する課やチーム全体で業務の見直しを検討する際は、チーム全体のタスクなどマクロな視点で棚卸しをすると同時に、係や数人のグループで行っている業務や、個人が抱えている業務までを棚卸しするミクロな視点をあわせもつ複眼思考が必要です。
そのために、管理監督者やプレイングマネジャーが係やチーム単位、あるいは個人単位までヒアリングを行い、それぞれの業務内容・細かいタスクから全体像を把握するようにしましょう。また、一方的なヒアリングでやらされ感を感じさせないようにするため、各人からの報告も安心してできるような雰囲気づくりと仕組みをつくりこめれば、より効果的です。
適切な業務体制の構築
ここでいう適切な業務体制とは、特定の人に業務が偏らず、各人のキャパシティを超えた業務量が課されていない状態のことを指します。非現実的なノルマを課したり、ボリュームある業務を特定の人だけで担当するような状態を意識、無意識つくってしまうと、上司への部下の信頼に傷がつく恐れも予想され、結果、本来目指すべき「仕事の見える化」が遠のいてしまいます。そのような事態を避けるためにも、上述の「業務内容のヒアリング」と、それを実施する際の雰囲気づくりがとても重要となります。
マニュアルの作成
業務のマニュアル化も「仕事の見える化」に繋がります。なぜなら、マニュアルを作成するプロセスでは、どうしても業務を細分化し、見える化する必要があるからです。ただし、マニュアル化を進める際に注意しなければならないこととして、いかに、関係者を巻き込んで一緒に楽しく進められるかがあります。また、マニュアル化が目的ではなく、あくまでも業務の平準化や共有、誰もが円滑に遂行できるようにするための手段の一つであることの徹底も重要です。これからの時代、人が行う仕事は、マニュアルプラスアルファの部分、価値提供が可能となる余地を残しておくことが重要なはずです。
日常業務をDX化
クラウドサービスをはじめとするIT技術を導入し、デジタル化、DX化を図るプロセスでも見える化に繋がります。なぜなら、導入にあたっては、ほぼ間違いなく、業務の切り分け、見える化が前提として必要となるからです。日常の仕事の中で、人が行う仕事とテクノロジーに任せる仕事を切り分けて、人は、人ならではの仕事に時間もエネルギーも集中する。そんな状態が構築できれば、働き方のアップデートにも繋がるでしょう。
仕事のDX化、見える化を通じて、より豊かに働ける状態を目指しましょう。
「仕事の見える化」にはタイムマネジメント研修が効果的
これまで見てきたように、「仕事の見える化」を進めるにあたっては、タイムマネジメント研修が役立ちます。タイムマネジメントとは、単なる時間管理をいうのではなく、効率的に仕事を進めるために必要な方法論をいいます。業務に直結した内容のため、受講後、即日実践可能です。タイムマネジメント研修は「仕事の見える化」以外にも、社会人として仕事を行う上で必要不可欠な考え方やさまざまなスキルが身につけられますので、特に、若手社員のうちに受講しておくことがおすすめです。
関連記事
■タイムマネジメント研修とは?実施する理由や効果まで包括的に解説します
■株式会社アイル・キャリアが提供するタイムマネジメント研修
タイムマネジメント研修の目的

タイムマネジメント研修の最大の目的は、働く人たち一人ひとりが、「より良く働き、より良く生きる」ことの実現にあります。組織には、スタッフ、プレイングマネージャー、管理職という3つの層がありますが、各々の立場や役割に合わせた「適切な」タイムマネジメント手法が存在します。
タイムマネジメント研修で特に重要なのは、効率化を図るべきものと、図ってはいけないものを理解することです。行き過ぎた効率化は、かえって「残業の削減」や「仕事の生産性」を悪化させることになるものです。
スタッフ・新人向け

スタッフや新人向けタイムマネジメント研修の目的は、決められた時間内で成果を出せるようになることです。1日24時間という与えられた時間の中で、いかに効率よく仕事を進めるかがポイントです。
研修では、個人でできる手法・工夫を中心に、周囲も巻き込んで取り組むノウハウについても一部学びますので、チームの段取りを効率化することにも繋がるでしょう。
また、ITに強いデジタルネイティブ世代として、DX視点での効率化を学び、提案する姿勢も求められます。上司に萎縮することなく、DX推進の必要性を伝えることができれば、上司や先輩社員の「残業削減」にも貢献するでしょう。
プレイングマネージャー・管理職向け

個人のタイムマネジメントはもちろん大切ですが、その取り組みを部署全体、チーム全体に波及させるためには、プレイングマネージャー・管理職が主体的に行動していく必要があります。
プレイングマネージャーの主な役割は、スタッフ・新人の「働き方」を整えることです。研修では、部下一人ひとりが「決められた時間内で成果を出せる」「特定の部下に業務が偏り過ぎないようにする」ための業務割り振りや指示の習得を目指します。これらを実行できれば、部署全体のムダな残業削減に役立つでしょう。
具体的には、既存の業務フローを整理して不要な工程をカットする、暗黙知を形式知としてまとめ、組織知として共有する仕組み作りなどの手法を身につけます。併せて、業務のあり方そのものを見直すための視点や、DX活用の必要性などについても学びます。
タイムマネジメント研修のコース例について

タイムマネジメント研修を行っている業者は多く存在しますが、その中でもアイル・キャリアが実施するタイムマネジメント研修は、他社と比較して多くのメリットや特徴があります。
今回ご紹介するプログラムは一例であり、研修内容を自由にオーダーしていただくことも可能です。お客様のお話を伺った上で「残業の減らし方」に特化したプログラムの作成も可能です。
| ~アイスブレイク&自己紹介~ | |
| 1.タイムマネジメント上手になるために
| 講義 |
| 《実習1》個人ワーク/ペアワーク
| 実習 |
| 2.段取りとタイムマネジメントの基本
| 講義 |
| 《実習2》個人ワーク/ペアワーク
| 実習 |
| 《実習3》グループワーク(事前課題)
| 実習 |
| 3.さまざまな段取り術
| 講義 |
| 《実習4》振り返り/グループ内共有
| 実習 |
| ※まとめ、質疑応答、アンケート記入/研修終了 | |
気軽に始められるオンライン研修

オンライン研修では、事前課題としてeラーニング視聴などを設定し、基本事項の事前学習を推奨しています。事前課題からの学びのシェアやグループワーク、できる先輩との対談といったプログラムを設け、集合研修以上に集中力が持続するような構成としています。
| ~アイスブレイク&自己紹介~ |
| 1.事前課題(動画視聴)の振り返り ● 事前課題の振り返りをグループ・全体で共有 |
| 《実習1》グループワーク ● テーマ「駅弁を作ろう!」 ● 指定された駅の中から1つ駅を選択し、駅弁を企画 ● 企画した駅弁を相互にプレゼン ● プロセスの振り返り・印象交換 ● グループ・全体で共有 |
| 2.事前課題(時間の使い方の見える化)の振り返り ● 事前課題の振り返りをグループ・全体で共有 |
| 《実習2》グループワーク ● テーマ「それ先輩に聞いてみよう。」 ● 各グループの先輩社員1人ずつが発表 ● 仕事の段取り、コミュニケーションなどのポイントをシェア ● パネルディスカッション・質疑応答 |
| 3.研修全体の振り返り ● 職場実践・行動計画をグループ・全体でシェア ● 質疑応答 |
| 4.終了 |
受講者様の声
1)仕事の優先順位は、必要以上にフレームワークにこだわらないことや、イレギュラーを見込んでスケジュールを立てることなど、業務に活かせることが多い講義だった。講師の先生も明るく分かりやすかった。
2)グループワークで他の課の仕事を聞け、そこで気を付けていることの話を聞けたことは、自分の仕事以外の角度の視点もあって参考になった。また「時間短縮だけがタイムマネジメントではない」という冒頭の言葉が、自分の思っていたタイムマネジメントと異なっていたので印象に残っている。
3)自分がなぜ仕事が遅いのかがよく分かった。今後は段取りを決めて仕事を進めていきたいと思った。
1)仕事を効率的に進めるためのテクニックをたくさん学ぶことができた。業務改善をどうしたら良いか分からなかったが、少しの工夫で色々変えることができると気づくことができた。
2)スキマ時間を見つけて、効率よく仕事をしていきたいと感じた。効率よく行うことは、プライベートな時間が増えるという事を意識して、スケジュール、書類、データ整理に取り組んでいきたい。
3)段取りについては今まで取り組んできたやり方でよいと気づけた。あとは個人の時間意識、優先順位の捉え方,コスト意識の持ち方が大切だと感じた。
負担軽減の講師派遣
アイル・キャリアの研修は、講師がお客様のもとに伺って研修を行う派遣形式を採用しています。そのため、研修会場はお客様にてご手配いただいております。自社の会議室や、外部の貸し会議室・レンタルスペース等、お客様のご都合の良い場所にて開催可能です。自社で開催する場合は、移動の手間や交通費のカットもできるため、お客様の負担軽減にもつながります。
関連記事
■タイムマネジメント研修とは?実施する理由や効果まで包括的に解説します
■株式会社アイル・キャリアが提供するタイムマネジメント研修
担当講師のコメント
「時間は有限」「時間の使い方は、人生の質を変える、キャリアを変える」
タイムマネジメントの本質は、「何のためにタイムマネジメントするのか?」をハッキリさせることです。「行き過ぎた効率化がもたらす弊害にも目を向ける重要性」にも触れつつ、タイムマネジメントの考え方、方法論、コツを紹介しています。

リモートで会社を経営しつつ、国内外を問わず年間200日以上のセミナー登壇を続ける。多忙な日常の中、「仕事と家庭、プライベートのバランスをどう取っていくのか」といった課題に対して、タイムマネジメントの重要性を実感するようになり探求、今日に至る。趣味は水泳、ランニング、ストレッチ、ヨガ、筋トレ、サーフィンなど。
【講師略歴】
2006年 株式会社アイル・キャリアを創業
2013年 海外(ベトナム)でセミナー講師デビュー
2019年 出版『稼げる講師、稼げない講師どこが違うか』(あさ出版)
2020年 東洋経済オンライン記事が週間アクセス数ランキング第一位を獲得
2021 年 世界最大の会員制人材開発組織 ATDジャパンサミットにて、DX スタディグループのメンバーとして登壇
2022 年 世界最大の会員制人材開発組織 ATD ジャパンサミットにて、DX スタディグループのメンバーとして登壇
まとめ
「仕事は減らない。でも、人は増えない」そんな課題を抱える組織は、当たり前のように思える「仕事の見える化」が業務改善のスタートラインとなるものです。「仕事の見える化」で仕事のムダ、ムラを省き、捻出した時間でテクノロジー活用の具体的検討、導入まで至って業務効率化が図れれば、時間外労働の削減はおろか、働き方改革も可能になるでしょう。あれこれ悩んでいる間に、まずは、タイムマネジメント研修を受講することをお勧めします。
この記事の監修者
株式会社アイルキャリアは、お客様ごとに抱える課題や目標に合わせたオーダーメイドプログラムで”学び”を提供する研修会社です。官公庁・自治体から上場企業、医療法人や学校法人まで様々なお客様に対して、ご要望と時流をふまえた必要な”学び”を、新人から管理職まで幅広く提供し、組織の人材育成を支援しております。特徴としては、その研修で達成したい目標(行動変容)の先にある成果、パフォーマンス(行動変容の結果得らえるもの)までを意識してプログラムを作成することにあります。
サイドメニュー
- ★選ばれる理由●
- 講師紹介
- 事例一覧2
- 川口鋳物工業協同組合様
- 愛媛県研修所
- 佐賀県自治研修所
- 蕨市役所
- IAC様
- 静岡県湖西市役所
- 佐倉市役所
- 千葉市
- 大分県自治人材育成センター
- 事例一覧3
- 下田市役所
- 宮崎県市町村職員研修センター
- 鹿児島県
- 江戸川区
- 足利市
- 宮崎県市町村
- 伊勢崎市
- 労働生産性の向上-1
- タイムマネジメントが上手い人の特徴とスキル:仕事の生産性を高める秘訣とは?
- 【タイムマネジメント研修とは】 実施する理由や効果まで包括的に解説いたします
- タイムマネジメント方法の完全ガイド
- タイムマネジメント能力を高めるための実践ガイド
- 効果的なタイムマネジメント研修の選び方
- 「仕事の見える化」は業務の効率化に必須 【タスクを可視化する研修を紹介】
- 仕事の優先順位づけとは? 業務を効率化するためポイント・研修を紹介
- イレギュラー対応力を分析して生産性を上げる 【すぐ使えるスキルから研修まで】
- チームパフォーマンス向上研修で変わる職場 【組織としての成長を目指して】
- 労働生産性の向上-2
- 正しい育成方法で新人・若手社員の早期育成を実現する 【研修で意識すること】
- 仕事の効率化に結びつく具体的な方法を提案 【即効性のある研修も紹介】
- 自律型人材とは?求められる背景やメリット・デメリット、育成方法を解説
- オンボーディングは早期離職を解決するカギ!実施時のポイントや事例も紹介
- 【新人の早期育成】 即戦力を育てるために取り組むべきことを解説します
- 時間管理の効果的な方法とツールの徹底解説
- 生産性を向上させるための秘訣とは 【組織レベルから個人まで対応】
- 時間の使い方が上手になる方法は? 成果が上がる時間管理術を紹介
- プレイングマネジャーの仕事術とは?役割や効率化のコツを解説
- 労働生産性の向上-3
- プレイングマネジャーの悩みを解決する時間管理術とは?
- タレントマネジメントとは?導入手順やメリット・デメリットも紹介
- テレワーク・在宅勤務導入後の労働時間管理におすすめの方法 3選
- スピード仕事術を身に付けよう!仕事を効率化させるテクニック
- タスク管理を上達させて仕事を効率化させよう! 役立つツールの紹介も
- 企業におけるエンゲージメントの意味とは? 向上させる方法もあわせて解説
- ハラスメントとは? 会社で重視すべき7つのハラスメントと防止策を解説
- リスキリングとリカレントの違いとは? 導入するメリット・デメリットを解説
- 社内コミュニケーションを活性化させる9つの施策を解説!他社の成功事例も紹介
- 労働生産性の向上-4
- Z世代の特徴や欠点に合わせた効果的な育成方法とは?NGな叱り方も紹介
- VUCAとは?今の時代に適した人材を育成する方法をわかりやすく解説
- 厚生労働省も推進するキャリア自律とは?定義やデメリット・メリットを紹介
- 人事担当者必見!戦略人事の成功事例8選&成果を出す実行ステップ
- 人的資本経営とは?企業・自治体が押さえるべき背景と人材育成の成功ポイント
- 残業削減のための研修や方法を解説!働き方改革で求められる施策
- Z世代も納得!「タイパを極める」ビジネススキル習得術
- ワークスタイル分析で生産性を高める 【すぐに使えるスキルから研修まで】
- 複製用
- 働き方-1
- キャリアデザインとは? 意味や必要性、具体的な支援方法を徹底解説!
- キャリアデザインシートの作成方法と活用の秘訣
- キャリアデザイン研修の効果と実践例
- キャリアデザインの重要性とその実践方法
- 【キャリアの定義とは?】 従業員のキャリア開発が必要な理由を解説
- キャリアの棚卸しの方法とステップガイド
- キャリアチェンジを成功させるための具体的な方法
- どんなキャリアを積みたいかわからない人への、 キャリアプラン作りの基礎解説
- キャリア戦略の重要性 | 人生設計や転職時に役立つワークシートを紹介
- 働き方-2
- キャリアデザインシートの書き方例 | 構成の方法やコツを解説
- キャリアゴールとは何か? ゴール設定の必要性や具体的な設定手法、事例を紹介
- ビジョン達成に必要な考え方やビジョン策定に必要な手順、 企業事例を解説
- キャリアプランニングとは何か? メリットや重要性、実施方法まで詳しく解説
- ビジネスにおいて目標設定が必要な理由とは? 目標設定の具体例やフレームワーク、職種別の例文を解説
- キャリアアセスメントとは? メリット・デメリットや活用できるツールを紹介
- 「生きがいを支える5つの大切なこと」
- 人生の満足度を高める方法
- 今注目の「働き方改革」とは?具体的な取り組みと課題
- 働き方-3
- ワークライフバランスの見直しや実施が 企業と社員にとって必要な理由
- 仕事と家庭の両立法 | 無理なくこなすためのコツ
- 研修理論-1
- 「研修は、人の能力を拡張する」が鍵に… ~「あなたに頼んでよかった」を生み出す、人の領域~
- 2026年 人材育成のトレンド
- 人材育成は、「人が決める場」をつくる仕事だ!
- 「High Impact Learningモデル」
- 「ラーニングピラミッド」
- テクノロジーと人間力を融合した学びの未来
- 「カークパトリックモデルの4段階評価」
- 「パーソナライズされた学習は、誤った仮説に基いている」
- 「知識の保持や適用には望ましい困難が必要」
- 研修理論-2
- 「学習の5段階」
- 「研修のゴールは行動変容ではない!?」
- オンライン研修とは?メリット・デメリット、始め方について徹底解説
- 「サクセス・ケース・メソッド」
- 「プランド・ハプンスタンス・セオリ(ハプンスタンス・ラーニング・セオリ―)」
- 「エキスパート(専門家)になるには」
- ニュース一覧
- 調達企業一覧(補足資料)
- 監修者
- 資料請求ありがとうございました
- 求人情報
- ピックアップ!
- 人材育成に関するコラム
- お客様の声(2022年度)
- お客様の声(2021年度)
- お客様の声(2020年度)
- 書籍購入
- 特典動画のお申し込み確認
- ダイレクトメール
- メディア掲載・その他
- 個人情報保護方針
- 無料個別相談会(オンライン)
- 無料個別相談会のお申し込み確認
- メールマガジン登録
- メルマガ登録ありがとうございました
- メルマガ登録を解除いたしました
- 研修一覧