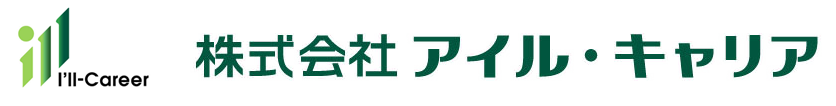ワークライフバランスの見直しや実施が
企業と社員にとって必要な理由
社員の離職率や職務満足度にお悩みの組織はとても多く、ワークライフバランスを意識した働き方へのシフトチェンジは必須となってきています。ワークライフバランスを整えることは、社員のモチベーションや業務の生産性・コストパフォーマンスの向上にも繋がる必要な要素です。本記事ではワークライフバランスを整えるメリットや必要な情報、研修のご案内などを紹介しております。
ワークライフバランスとは?

ワークライフバランスとは仕事と生活の調和が取れていることを指します。社員のための働き方ではなく、企業にとっても必要不可欠なものです。平成19年には内閣府から指針が策定され、企業だけでなく自治体も一丸となって取り組む問題となっています。
ワークライフバランスの正しい意味
「ワークライフバランス=仕事と生活の調和」であることを説明しましたが、これは性別や世代に左右されず全員が意識すべき働き方です。さらに、仕事とプライベートのいずれかを優先させるのではなく「調和」させることがポイントです。きちんと仕事とプライベートのバランスが取れることによって、生きがいや喜びを生み出すことができます。有意義で充実した人生を送るためには、ワークライフバランスを意識することが不可欠であると言っても過言ではないでしょう。
ワークライフバランス憲章とは?
「ワークライフバランス憲章(仕事と生活の調和憲章)」とは、仕事と生活の調和推進のために平成19年12月に内閣府によって策定された指針のことを指します。仕事と生活の調和を国民に推進することを通じて、経済成長、出生率の向上、そして持続可能な社会の実現につなげることが目標です。東京都では、「ワークライフバランス認定企業」への表彰などを実施しています。ワークライフバランス認定企業として表彰されると、企業のイメージアップになり、求職者や応募者が増加することにもつながるでしょう。
関連記事
■今注目の「働き方改革」とは? 具体的な取り組みと課題
■株式会社アイル・キャリアが提供するタイムマネジメント研修
ワークライフバランスを充実させるメリット

ワークライフバランスを充実させることで、家族や友人との時間、自分の時間を大切にすることができ、人生の満足度向上にもつながります。また、プライベートだけでなく、時間の有効活用により自身のスキルアップにも時間を費やすことができ、仕事へのモチベーションアップにも効果が期待できるでしょう。主に以下3つのメリットがあります。
1. 自己実現が達成しやすくなる
ワークライフバランスを保つことができると、プライベートの時間をしっかりと確保できます。プライベートの時間に家族や友人など大切な人と過ごしたり、自身のスキルアップのために何かを学んだり、副業したりなど、本業以外の取り組みに時間や労力を割いて自分の意向に沿った行動が取れるようになります。自己実現が達成しやすくなるため、必然的に人生の充実度や満足度が向上するはずです。
2. 仕事に対するモチベーションアップ
休日出勤をしたり残業が続いたりすると、オンとオフの切り替えが難しくなり、心と身体のバランスを整えることが難しくなるものです。プライベートの時間もしっかりと確保して仕事とプライベートのメリハリをつけることで、仕事に対するモチベーションが上がることが期待できます。
3. 家庭と仕事の両立・個人に合わせた働き方ができる
近年、働き方改革や新型コロナウイルスの影響で、リモートワークや時短勤務など多様な働き方が認められるようになりました。しかし、仕事をしたくても子育てや介護を理由に、仕事を辞めざるを得ないのが実情です。ワークライフバランスが取れる企業であれば、そのような人々でも安心して仕事ができ、家庭や仕事が両立しやすくなるでしょう。
また、個人に合わせた働き方の実現によって、これまで働きたくても働けなかった人の経済的な自立にもつながることも考えられます。
ワークライフバランスが企業に必要とされている理由

「ワークライフバランス」と聞くと、社員側にしかメリットがないと感じるかもしれませんが、企業側にも数多くのメリットがあります。社員のモチベーション向上や職務満足度の向上は企業の成長に大きな影響を及ぼします。また、離職率の低下や優秀な人材の確保にもつながるため、社員のワークライフバランスを意識した改革に取り組む企業が増えています。
優秀な人材の獲得・定着率アップ・人手不足の解消
近年、少子化による人口減少により労働人口も減っています。つまり求職者側や転職者の売り手市場になっているということです。この傾向は今後ますます進んでいくことでしょう。
また、結婚、育児、介護などさまざまなライフイベントによって働きたくても働くことに不安を感じている潜在的な求職者も数多くいます。実際に働いている人でも、「育児や介護のための時間が取れずフルタイムでの勤務が難しい」「時短勤務制度がない」などの理由で離職する人は少なくありません。
ワークライフバランスが実現できる企業は、「働きやすい」「従業員を大切にしている」というイメージを求職者に与えるため魅力的に映り、応募者数が増加して人手不足が解消されたり、定着率アップや優秀な人材の確保につながったりする可能性が高いものです。
時間外労働の削減
2021年にOECDが発表した「世界各国の年間平均労働時間」によると、日本は1,607時間/年となっており、アメリカや韓国に次いで多い結果となりました。そして、労働生産性に関してはOECD加盟国38カ国中28位の$78.6となっており、平均の$100.7を下回っています。日本の労働時間は年々見直されるようになってきていますが、まだまだ不十分であると言わざるを得ないでしょう。日本の非効率的な働き方の大きな要因の1つが「長時間にわたる時間外労働」です。時間外労働は社員のモチベーションを下げ、離職率を上げることにもつながりかねません。業務の効率化が必要とされています。
業務効率化は、下記メリットがあります。
- 人件費の削減
- コストパフォーマンスの向上
- タイムパフォーマンスの向上
社員のモチベーションアップ・生産性の向上
「仕事」が生きがいである人ももちろんいますが、有意義で充実したプライベートにするために仕事を頑張るという人が大半なのではないでしょうか。
2006年に内閣府が発表した「両立支援・仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)推進が企業等に与える影響に関する報告書概要」によると、ワークライフバランスが取れる企業で働く従業員は仕事へのモチベーションが高いことが分かりました。社員のモチベーションの高さは企業の成長にとても重要なものです。また、オンとオフのメリハリがしっかりつけられると従業員のパフォーマンスや職務満足度が向上し、生産性の向上にもつながります。
企業が実施すべき必要な取り組み

前章では企業がワークライフバランス向上に取り組むメリットについて説明しました。しかし、いざ働き方改革をしようと思っても、何から始めれば良いのか分からず途方に暮れてしまう方や企業も多いのではないでしょうか?
社員にとって理想的なワークライフバランスを保つために、休暇制度や福利厚生などの制度の整備をすることも大切ではありますが、それだけでは不十分です。影響範囲を考えて、適切な判断をすることが求められます。ここでは、企業が取り組むべき内容について紹介します。
休暇制度や福利厚生が利用しやすい環境や雰囲気
従業員のワークライフバランスの実現に向けて新しい制度や施策を始めても、有名無実化することもあります。たとえば、新しい制度や施策を導入してもそれらを活用できるような雰囲気や環境でない場合は、従業員は利用しづらいでしょう。ワークライフバランスを社内に浸透させていくためには新しい制度を導入するだけでなく、会社全体で意識改革を進めることが大切です。経営陣や管理職が先陣を切って新しい制度を活用したり、社内報に利用者の声を掲載したりするなどして、ワークライフバランスを実現するための土壌づくりをすることをおすすめします。
下記は内閣府の施策例です。ぜひ参考にしてください。
【休業制度】
- 育児休業
- 介護休業
- 求職者の復帰支援
【休暇制度】
- 看護休暇
- 配偶者出産休暇
- 年次有給休暇の積立制度
- 有給を利用した連続休暇
【働く時間の見直し】
- 勤務時間のフレキシビリティ(フレックスタイム制度・就業時間の繰上げや繰下げなど)
- 時短勤務(勤務日数を減らす・勤務時間を減らす・週3勤務・週4勤務など)
- 変形労働時間(一定の労働期間内での労働時間を柔軟に調整する)
- 時間勤務の見直し(ノー残業デー、残業の事前申告制など)
【働く場所の見直し】
- 勤務場所のフレキシビリティ(在宅勤務制度・サテライトオフィス制度・テレワーク・リモートワーク・ワーケーションなど)
- 転勤の限定
【その他】
- 経済的支援(業務に関わる資格の受講料や受験料を会社が全額負担または一部負担する・出産や子どもの成長に合わせた祝い金の支給など)
- 事業所内保育施設
- 再雇用制度
- 育児・介護・家事代行・食事提供の情報提供・相談窓口の設置
定期的な制度の見直し
ワークライフバランスが実現できているホワイト企業であっても、最初から簡単に取り組みや改革が成功したわけではありません。成功企業は従業員が制度を利用できているか、仕事と私生活のバランスは取れているかなど、社員へのヒアリングや調査を実施したり、勉強会を開催したりと定期的に見直しして改善してきました。時代は常に変わりゆくものであるため、社員のニーズも時代と共に変化する可能性があります。常に改善、アフターフォローをすることで、職務満足度の維持または向上、そして社員の離職の防止につながるでしょう。
ワークライフバランスに関する社内改革を進める際には、定期的な調整や見直しをするように心がけましょう。
まとめ
企業は社員の働き方や満足度などに大きな影響を与えます。社員のワークライフバランスを意識した働き方改革は企業成長に大きく近づけるための重要な取り組みであるため、企業だけではなく自治体や国も一丸となって取り組んでいる問題です。
転職が当たり前となった現代では、求職者はワークライフバランスを意識した転職活動をすることが多く、優秀な人材の確保にもつながります。また、離職率の低下、社員のモチベーションアップなど企業へのメリットは多くあります。社員にとっても私生活を大切にしながら仕事に励むことができる環境は自己実現や人生の満足度向上にもつながるため、ワークライフバランスは重要な取り組みです。
休暇制度や福利厚生が利用しやすい環境や雰囲気作りに励んだり、定期的な制度の見直しをしたりすることでワークライフバランスが取れる組織に変革していきましょう。
関連記事
■今注目の「働き方改革」とは? 具体的な取り組みと課題
■株式会社アイル・キャリアが提供するタイムマネジメント研修
<<前の記事 次の記事>> 今注目の「働き方改革」とは?具体的な取り組みと課題 仕事と家庭の両立法 | 無理なくこなすためのコツ
この記事の監修者
株式会社アイルキャリアは、お客様ごとに抱える課題や目標に合わせたオーダーメイドプログラムで”学び”を提供する研修会社です。官公庁・自治体から上場企業、医療法人や学校法人まで様々なお客様に対して、ご要望と時流をふまえた必要な”学び”を、新人から管理職まで幅広く提供し、組織の人材育成を支援しております。特徴としては、その研修で達成したい目標(行動変容)の先にある成果、パフォーマンス(行動変容の結果得らえるもの)までを意識してプログラムを作成することにあります。
サイドメニュー
- ★選ばれる理由●
- 講師紹介
- 事例一覧2
- 川口鋳物工業協同組合様
- 愛媛県研修所
- 佐賀県自治研修所
- 蕨市役所
- IAC様
- 静岡県湖西市役所
- 佐倉市役所
- 千葉市
- 大分県自治人材育成センター
- 事例一覧3
- 下田市役所
- 宮崎県市町村職員研修センター
- 鹿児島県
- 江戸川区
- 足利市
- 宮崎県市町村
- 伊勢崎市
- 労働生産性の向上-1
- タイムマネジメントが上手い人の特徴とスキル:仕事の生産性を高める秘訣とは?
- 【タイムマネジメント研修とは】 実施する理由や効果まで包括的に解説いたします
- タイムマネジメント方法の完全ガイド
- タイムマネジメント能力を高めるための実践ガイド
- 効果的なタイムマネジメント研修の選び方
- 「仕事の見える化」は業務の効率化に必須 【タスクを可視化する研修を紹介】
- 仕事の優先順位づけとは? 業務を効率化するためポイント・研修を紹介
- イレギュラー対応力を分析して生産性を上げる 【すぐ使えるスキルから研修まで】
- チームパフォーマンス向上研修で変わる職場 【組織としての成長を目指して】
- 労働生産性の向上-2
- 正しい育成方法で新人・若手社員の早期育成を実現する 【研修で意識すること】
- 仕事の効率化に結びつく具体的な方法を提案 【即効性のある研修も紹介】
- 自律型人材とは?求められる背景やメリット・デメリット、育成方法を解説
- オンボーディングは早期離職を解決するカギ!実施時のポイントや事例も紹介
- 【新人の早期育成】 即戦力を育てるために取り組むべきことを解説します
- 時間管理の効果的な方法とツールの徹底解説
- 生産性を向上させるための秘訣とは 【組織レベルから個人まで対応】
- 時間の使い方が上手になる方法は? 成果が上がる時間管理術を紹介
- プレイングマネジャーの仕事術とは?役割や効率化のコツを解説
- 労働生産性の向上-3
- プレイングマネジャーの悩みを解決する時間管理術とは?
- タレントマネジメントとは?導入手順やメリット・デメリットも紹介
- テレワーク・在宅勤務導入後の労働時間管理におすすめの方法 3選
- スピード仕事術を身に付けよう!仕事を効率化させるテクニック
- タスク管理を上達させて仕事を効率化させよう! 役立つツールの紹介も
- 企業におけるエンゲージメントの意味とは? 向上させる方法もあわせて解説
- ハラスメントとは? 会社で重視すべき7つのハラスメントと防止策を解説
- リスキリングとリカレントの違いとは? 導入するメリット・デメリットを解説
- 社内コミュニケーションを活性化させる9つの施策を解説!他社の成功事例も紹介
- 労働生産性の向上-4
- Z世代の特徴や欠点に合わせた効果的な育成方法とは?NGな叱り方も紹介
- VUCAとは?今の時代に適した人材を育成する方法をわかりやすく解説
- 厚生労働省も推進するキャリア自律とは?定義やデメリット・メリットを紹介
- 人事担当者必見!戦略人事の成功事例8選&成果を出す実行ステップ
- 人的資本経営とは?企業・自治体が押さえるべき背景と人材育成の成功ポイント
- 残業削減のための研修や方法を解説!働き方改革で求められる施策
- Z世代も納得!「タイパを極める」ビジネススキル習得術
- ワークスタイル分析で生産性を高める 【すぐに使えるスキルから研修まで】
- 複製用
- 働き方-1
- キャリアデザインとは? 意味や必要性、具体的な支援方法を徹底解説!
- キャリアデザインシートの作成方法と活用の秘訣
- キャリアデザイン研修の効果と実践例
- キャリアデザインの重要性とその実践方法
- 【キャリアの定義とは?】 従業員のキャリア開発が必要な理由を解説
- キャリアの棚卸しの方法とステップガイド
- キャリアチェンジを成功させるための具体的な方法
- どんなキャリアを積みたいかわからない人への、 キャリアプラン作りの基礎解説
- キャリア戦略の重要性 | 人生設計や転職時に役立つワークシートを紹介
- 働き方-2
- キャリアデザインシートの書き方例 | 構成の方法やコツを解説
- キャリアゴールとは何か? ゴール設定の必要性や具体的な設定手法、事例を紹介
- ビジョン達成に必要な考え方やビジョン策定に必要な手順、 企業事例を解説
- キャリアプランニングとは何か? メリットや重要性、実施方法まで詳しく解説
- ビジネスにおいて目標設定が必要な理由とは? 目標設定の具体例やフレームワーク、職種別の例文を解説
- キャリアアセスメントとは? メリット・デメリットや活用できるツールを紹介
- 「生きがいを支える5つの大切なこと」
- 人生の満足度を高める方法
- 今注目の「働き方改革」とは?具体的な取り組みと課題
- 働き方-3
- ワークライフバランスの見直しや実施が 企業と社員にとって必要な理由
- 仕事と家庭の両立法 | 無理なくこなすためのコツ
- 研修理論-1
- 「研修は、人の能力を拡張する」が鍵に… ~「あなたに頼んでよかった」を生み出す、人の領域~
- 2026年 人材育成のトレンド
- 人材育成は、「人が決める場」をつくる仕事だ!
- 「High Impact Learningモデル」
- 「ラーニングピラミッド」
- テクノロジーと人間力を融合した学びの未来
- 「カークパトリックモデルの4段階評価」
- 「パーソナライズされた学習は、誤った仮説に基いている」
- 「知識の保持や適用には望ましい困難が必要」
- 研修理論-2
- 「学習の5段階」
- 「研修のゴールは行動変容ではない!?」
- オンライン研修とは?メリット・デメリット、始め方について徹底解説
- 「サクセス・ケース・メソッド」
- 「プランド・ハプンスタンス・セオリ(ハプンスタンス・ラーニング・セオリ―)」
- 「エキスパート(専門家)になるには」
- ニュース一覧
- 調達企業一覧(補足資料)
- 監修者
- 資料請求ありがとうございました
- 求人情報
- ピックアップ!
- 人材育成に関するコラム
- お客様の声(2022年度)
- お客様の声(2021年度)
- お客様の声(2020年度)
- 書籍購入
- 特典動画のお申し込み確認
- ダイレクトメール
- メディア掲載・その他
- 個人情報保護方針
- 無料個別相談会(オンライン)
- 無料個別相談会のお申し込み確認
- メールマガジン登録
- メルマガ登録ありがとうございました
- メルマガ登録を解除いたしました
- 研修一覧